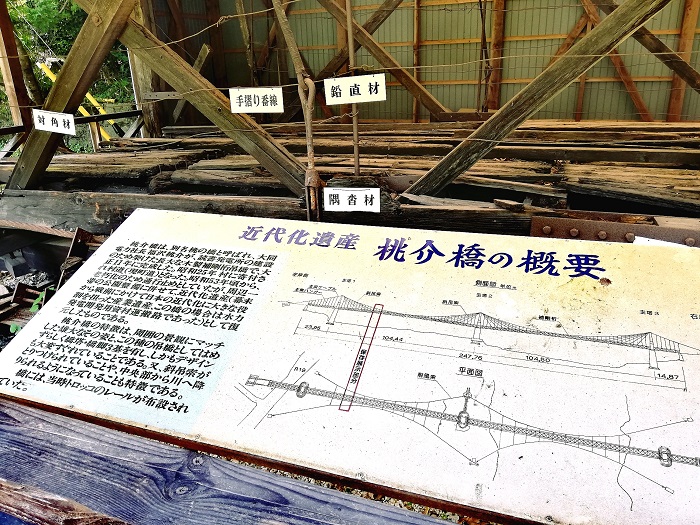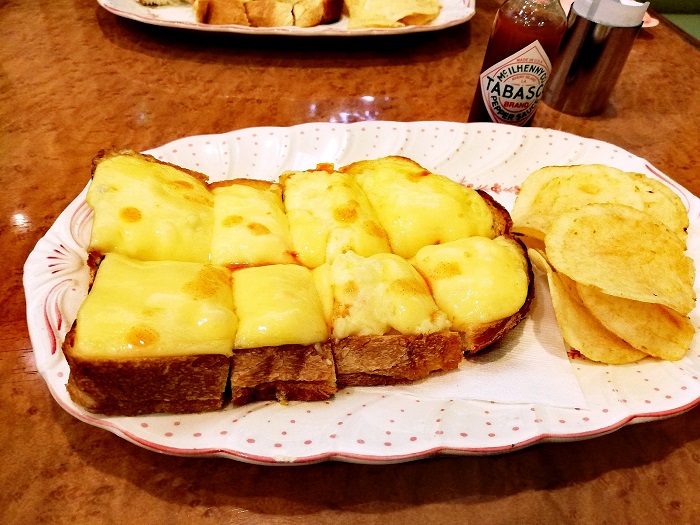上記ふたつの記事の続き。
後編の目次:
復路 下り坂
-
石段街の中心にて


朝早く起床して、旅館の部屋から外に意識を向ければ、それはもう見事としか言いようのない美しい空模様。昨日のものとは大違いで、まさに「こういうやつ」が見たかったのだと頷いた。
あの感じはあの感じでまた違った良さと風情ある雰囲気を醸し出していたから、別に初日の曇天が残念だと思っていたわけではなく、どうせ2日間を過ごすのならそれぞれ異なる伊香保の表情を見られた方が得だ、となんとなく考えていただけ。果たして、願いは叶えられたのだった。
そして何より胸に名状しがたい感覚をもたらしたのが、この場所らしさが非常によく出ている独特の空気。人っ子一人通らない宿泊施設の前の路。どこか現実離れしている要素、それぞれの在り方。各客室には多くの旅行客が滞在しているのだろうに……そう、人間だけではなくて、建物も街自体も、目覚めていながら半ば眠りの中にいるような様子だった。
神社の鳥居から途切れず伸びている階段は、確かに、人ならざる者が音もなく行き来するためのもの。神様だって妖怪だって隔てなく、温泉が好きなのだ。そう納得させられる。



ある土地に温泉が湧く。すると、それに浸かりたい人々がどこからかやってきて、やがて彼らをもてなす商売の形態が生まれ、旅館や遊技場が集まって町になる。そういう当たり前のことが私にはいつも新鮮で面白く感じられ、だからこそ温泉自体もそうだし、広義の「温泉街」がかなり好き。
その性質として、昼と夜ではがらっと雰囲気が変わるところにも注目したい。街が最も活気づくのは午後、夕方から夜にかけてだ。
朝に旅館を出て、温泉地を去ろうとしているときの寂しさはかなり独特だと思う。けっして悲しい、と言っているのではない。ものさびしいとかうらさびしいとか、そういう音にしか乗せられない、あの感じ。土地と人の半分が眠っている中を、自分は起きて闊歩している状態。すると、胸に去来する何か。たまに朝までずっと起きていて、街灯が消える瞬間を見たい……と考える時もある。
一晩眠って目を覚ますと、町が全然知らない顔になっている。そう、それ、本当にそういう印象があるのだった。前日の夕方に着いて知った空気の香りも、壁の色なんかも、次の日の払暁を過ぎればことごとく変わって見える。あんなに沢山話したのに、もう相手の名前すら憶えていない、なんて言いたげに。


伊香保の名物、石段街。
とりあえず歩いてみるのは賑やかで明るい表の通り。目に入った「湯乃花饅頭」の店や、左側に続く路地(後述する)の影響で佇まいが意味深長な、現在は物産店や遊技場として営業しているらしい「つたや物産店」の建物が気になるところ。隅っこが丸くて角がなく、可愛い。付近にはその店名が掲げられた街灯も見つけられた。このあたりで忘れずに、おまんじゅうを買う。
金曜日に到着して、こうして午前から街を散策していたのは土曜日のことになる。人通りも活気もそれなりにあった。寂れているのかと聞かれれば否、といえる程度に。だから尚更なのか、坂の上の方で見かけた邦来館の廃墟しかり、閉館した橋本ホテルしかり、廃業後の旅館跡がわりと多くそのまま残っているのに気が付かされる瞬間が興味深い。昔はおそらく、現在の数倍は栄えていたところなのだろう。伊香保の地は。
比較的規模の大きく、何より石段街で最も大きな中心の通りに面している中で、目立った廃墟が「村松旅館」。営業しているのかと最初は思ったが違った。メインのエリアにあってこの状態のまま残されているというのも珍しいというか、やはり、解体か再利用にもお金や手間がかかってしまうものなのか。


村松旅館はどうやら2006年までは営業していたらしかった。近代遺産で廃墟となっている「伊香保観光ホテル」の廃業が2007年だから、このあたりがわりと大きな変化の時期だったのかもしれない。
石段を下り、歩きながら考える。万葉集にも地名が記載されていたくらい、温泉自体は古くから湧いていた。やがて、こんな風に階段自体が街の核を形成する、傾斜の特徴的な伊香保の姿へと変化していったその基盤は、一体いつごろ固められたものなのだろう。
調べてみると今ある街の原型は16世紀後半に遡ることができそうで、かつ現在ある石段に御影石が敷かれたのが、昭和55~60年頃だそう。
真っ直ぐに一直線、ではなく、ところどころ軽く折れ曲がりながら伸び、部分的に踊り場が設けられている階段。上に行けば行くほど狭く、反対に裾野へ向かえば幅がぐっと広くなる。ところどころ洋風の電灯が立っているのがまた魅力的で、個人的に好きな要素が多く、全体の造形も楽しめる場所だと思った。
街の中に比較的大きな高低差があり、はっきりした主要部分から路が枝分かれしていて、ある種の統一された空気が漂っていながら細部が多様。そういうスポットが自分の嗜好に合致するのかもしれない……?
岐阜の馬籠宿などもそうだった。振り返ってみれば。
-
木の樋で湯を分ける


施錠されたガラスの扉。特徴的な覗き穴。
石段街の要所に設けられた観覧所から見えるのが何かといえば、湯樋、である。栗の木を用いて作られた湯樋と、そこを勢いよく流れ落ちていく、毎分約4000リットル湧出するとされる「黄金の湯」の源泉。これは江戸時代、寛永16年に井伊直好が採用したシステムが今に受け継がれているもので、源泉を引く権利を持つ各旅館に湯を決められた分量だけ配分するためのものだった。
小間口には切り落としの細工が施されている。なので、もしも源泉の湧出量が急激に増えることがあっても、そこから各旅館へ分配される湯の量は一定で同じ。そのようにして源泉周辺の権利が守られ、分けられた湯が旅行客に提供されているのだった。
この切小間(切こ満)の湯樋は数年に一度の点検と改修が必要で、その際は源泉の利用権を有する者たち全員が一堂に会し、不正などがないよう一部始終を見守ることになっている。特に切り落とし部分の打ち替えに関しては、その都度前の寸法を測って行っているというから、相当に神経を使うのだろう。

ガラス越しに流れ落ちる湯と、隙間から立ちのぼる湯気を眺めたり、地下から聞こえる轟音に耳を澄ましたりしていると、どきどきする。街の心音、その鳴動に間近で触れているような気がするし、実際にそうなのだから。湯の源泉こそが温泉街の血液であり、生命そのもの。仮に失われれば街もない。
石段街を通る人間の足下には湯樋がある。そこを休まず通り抜けていくものがあること、意識するのとしないのとでは散策の面白さが雲泥の差。
ちなみに私達の泊まった横手館も権利者組合に名を連ねる宿のうちのひとつで、定められた湯の分配量は7分(しちぶ)となっていた。伊香保では御三家と呼ばれる旅館へ配られる湯の量が多めで、例えば、その筆頭の千明仁泉亭への配湯量なら9分7厘だと組合のウェブサイトに記載されている。
-
あやしい一角
唐突に、予期せず「お楽しみの時間」がやってきた。
ここは湯の香通り。



こういう一角を日本中どこに行っても探している。伊香保にあるものも、実に風情があって良い、静かな通りであった。
料飲組合……観光協会推奨の店……18歳未満の方お断り……青山旅館……スナック石段。それに斜めの取手が二本並んだドア。もうほとんどの店舗が営業しておらず、人間の影もない。豆腐に文字を書いたみたいな四角い看板も、上のところが丸い入り口も、私にとって目印のような存在だった。
もの寂しさと、そこはかとないあやしさとを併せ持った魅惑の場所。それなのに、私は発見するとどうしても落ち着いていられなくて「あ、ちょ、ちょっと一瞬石段から横に逸れていい? 良いもの見つけちゃった……覗いてくる、本当いきなり奇矯な動きしてごめんね……」って脇の友達に言いながら移動をしていた。
正気を保つのが難しい。
しばらく意識を飛ばして魅力的な建物に全力で駆けて行ったり、街中にあるぐっとくる一点に引き寄せられて無心で何枚か写真を撮ったり、急に奇行種みたいなことをしても構わずそこに居て待っていてくれるのでみんな優しいと思う。今後も、なまぬるい眼差しで見守っていてほしい。




飾りとしての瓦の庇。正方形の豆タイル。2階の欄干。
どれも合言葉を彷彿とさせる要素で、それゆえ彼らに出会える場所は視覚的な狙い目だった。しかし短い中にぎゅっと見どころが凝縮されている道でたまらず、全体をこのまま保存して縮小し持ち帰りたくなる。適当な魔法をかけて。
さっき湯の花まんじゅうを買ったつたや物産店がメインの通りとの境目になっているため、いっそうこの特定の空間の、ちょっとうらぶれた感じが引き立っていた。そこで全盛期に遊ばれていたのは、射的でもダーツでも輪投げでもなかったはず……。
かつて路地のいちばん奥にあったのが有明館。すでに廃業・閉館しているけれど、建物は残っている。
石段街自体が賑わっていても横道には誰もいない、こういう領域も伊香保には多くあって、もう少し階段を下ったところにある道もそのうちの一つだった。
-
近代の建築物


ここは、群馬銀行伊香保出張所が昭和21年からしばらく入っていた建物。地下1階建て、地上2階建て。
横の階段を下りれば裏側も覗けるようになっている。正面から仰ぐと「香月」なる四角い看板の文字が残っていて、おそらく銀行でなくなった後は、飲食店や宿として使われていたのだろうと伺えた。あまり知られていなさそうだけれどとても良い。木の扉も、そこに嵌まったガラスの色や質感も。もう、中に立ち入る人間はまったくいないのだろうか。どんな風に管理されているんだろう。
裏の方に回ってみた時のこの感じ。建築物がひしめく場所では必然的に生まれる、けれど表には晒されない空間の妙。随分とほこりっぽくて、あまり長い間滞在しても息が詰まるが、たまに下りて行きたくなる性質の何か。そうだ、猫になってみたい。しなやかな猫の身を自由にすべらせたり、軽やかに跳躍したりして、街を歩き回れたら。何にせよ人間の散策には向かない場所らしい。
暗がりに対峙すると、待ち構えているようにある逆さまのキリン(KIRIN)。



その向かいにあるのが昭和20年に建てられた建造物。
こちらは写真屋から演芸場へと役割の推移したものだった。軒下に「さくらフィルム」の看板がある。この名称は、合併前のコニカ株式会社がむかし販売していたフィルムの商品名で、おそらくは「コニカカラー」よりもっと前……「さくらカラー」と呼ばれていた頃に設置されたものなのだろう。
看板は結構珍しいらしいので、じっくりと観察した。黄と緑と黒の組み合わせがかわいい。吊るされた赤い提灯と、繁茂する草も建物によく馴染んでいて、向かいにある元銀行の建物とは大きく異なり現役の施設として生きている感じがする。夜になったらどんな明かりがつくのだろう。
ここに至るまで、だいぶ石段坂を下ってきた。前編に引き続き特別なことは何もせず、ただ歩いているだけなのに、こんなにも楽しい。
-
玉こんにゃく串を片手に
このショーケースの感じ、好きだな。
昔の煙草販売ブースを思わせる、出窓みたいな部分。「木のおもちゃ」と書いてありお土産が並んでいる。資生堂化粧品、の文字が残っているが化粧品は見当たらない。



そして魅惑の木の欄干に出会ったのは細い道。近くに段差があるから自分の足元と同じ高さに屋根が並んで重なり、見渡すと、錆色の海が空中で波を寄せているように思える。鞠を持った子供の影が、その上を跳躍しながら駆けていく幻を見た。
大通りに戻ってくると、道行く人々が玉こんにゃくの串を持っている。
近くに売っているお店があるみたいだったので、さっそく探して買ってみることに。1本100円。その手軽さに、もうだいぶ長い間行っていない縁日の屋台などを連想させられて、懐かしい気分になった。あ、あれも食べたい。割り箸の先でうすいモナカの板に挟まれた、水飴というやつ。
私は普段、こんにゃくを頻繁には食べない。
だからきちんとそのおいしさを理解できるか不安だったけれど、全然大丈夫だった。

串に刺さった3つのまあるいこんにゃく。その数と同じく、三口でさくっと食べ終われるだろうと思いきや、これが見た目よりもなかなか量がある。しかもできたてで熱い。猫舌の自分には致命的であり、少しずつ冷ましながらかじりつつ、時間をかけてなんとか食べきった。
弾力のある白いこんにゃく本体。しょっぱくてほんのり甘い出汁が染みているのは、主にその表面、つまり外側だけだ。だから最初は、味が薄くて物足りなくなってしまうのでは、と危惧していたものの、内側は内側でこんにゃく自体の豊かな風味が確かにあり、噛んでいると舌に優しく感じられた。
そう、優しい。口と胃に穏やかに作用してくる食べ物、という印象で、ゆっくり咀嚼していると想像以上に満足感をもたらす。なお、店頭にからしが置いてあるため、お好みで辛さを調節できるのも良い点だ。
「ぷるぷる」のこんにゃく。
近くで発見した歌えるスナックの店名は「るんるん」。


満喫している。伊香保温泉を。
-
旧ハワイ王国公使別邸
辿り着いた石段街の最下段エリア、平らに整備された土地の片隅に、ぽつんと邸宅が残っている。
木の色や木目の模様がきれいな感じの家。
それが旧ハワイ王国公使別邸なのだと知り、一体ハワイの公使と伊香保の土地にどんな縁があったのか……? と、頭をひねった。この日は別邸内部が公開されていない日だったので、ひとまず外観だけ堪能し、後から詳細を調べてみることにして。あたりでは木造建築の良い香りがした。

どうやらこの建物は、ロバート・W・アルウィンという、駐日ハワイ王国弁理公使だった人物が伊香保に設けた別邸を、移築保存し公開している施設らしい。
ハワイも温暖な地域だが、やはり日本の高温多湿を極める夏には辟易したと見えて、アルウィン氏は避暑地を探していた。そこで、当時の政府高官であった井上馨が紹介したのが伊香保の地。それからも長く日本に暮らした公使はこの場所を愛し続け、今では坂のふもとの「アルウィン公園」にもその名前が刻まれるほど、伊香保に由縁のある人物となった。
そんなアルウィン公園こそが、伊香保石段街の終着点。


ときおり路地に逸れながら階段を下ってきたのは良いルートだったと思う。下からではなく、飲泉所から神社に至る道の方から散策を初めて、遠景の山を眺めながら徐々に下りていく。
坂の上で湧いた源泉が木の樋を伝って流れてくる様子さながら、順路に身を任せて歩いてきたからなおさら面白かった。
これは余談だが、帰りに渋川駅行きのバスに乗っていると、ある看板が道路に立っていた。「うまい焼肉 あおぞら」という食事処のもので、この先〇〇メートル……という表記の下に「豪華トイレ」と書いてあったのが衝撃的かつ印象的で、未だに気になっている。
検索すると色々情報が出てきて、料理は確かにおいしいが、お手洗いは特に豪華でもなく普通らしい。謎だった。
もともと自分はお風呂が好きだけれど、温泉にはさほど関心を持ってこなかった人間なので、今後も周囲におすすめを尋ねたり連れて行ってもらったりしながらゆるく多種多様なお湯と温泉地を楽しみたい。