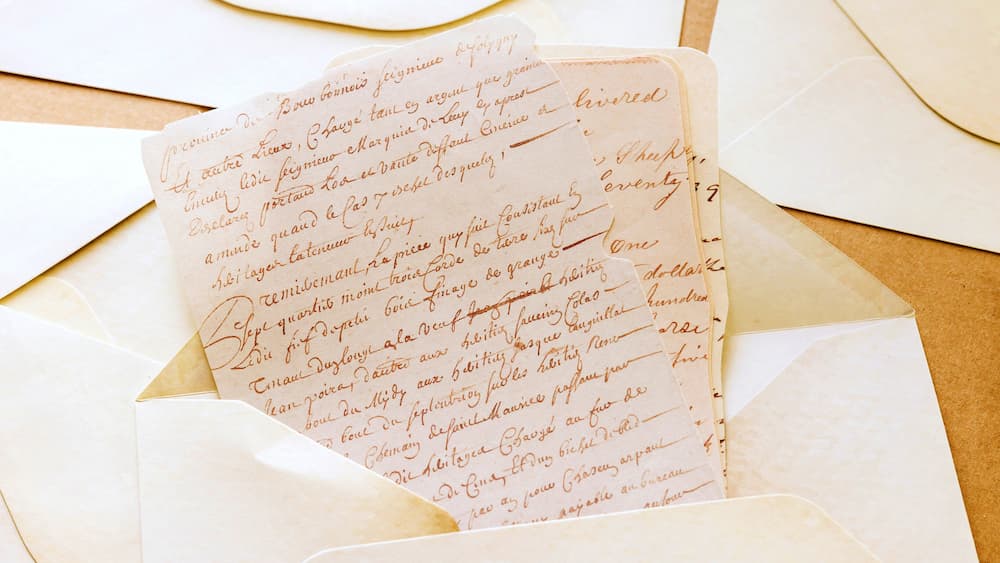月曜日に記事公開。その後、1日ずつ順次追加されます
週間日記・2023 10/2㈪~10/8㈰
10/2㈪「10月へようこそ」
やっとこの時期がやって来た。
10月の夜を愛している10月生まれだから、今が本当に過ごしやすくてずっと終わってほしくない。
でも、たとえ10月の秋が過ぎ去ってしまったところで、「私達」にはそこまで影響がないのだ。頭の中にいつでもこの季節を飼っており、必要ならそこへ行くことができる。ただ、それにどれだけの労力を要するか、その違いが体感する現実との軋轢として現れてくる。そういう人間達にとっては。
春や夏は本当に生きるのが大変な季節。花粉や猛暑に辟易しながら束の間の秋を思うのは、それはそれで楽しいこと。一方で冬は訪問。憧れていて、かねてより遊びに行きたいと願っていた子の家にようやく上がらせてもらうような気分で、外を歩ける。だから冬も好きだった。
大きなティーポットに牛乳をなみなみ注いで、そこにアマレットを混ぜて、寝る前に飲む。杏仁豆腐の味だ。これはそのまま飲んでもおいしい。28度なのでさほど強いものではないけれど、それでもきちんと喉や舌がぴりぴりするリキュールは大好き。ときどき、アブサンや電気ブランが恋しくなる。あれらは良い。
今日は2冊本を買った。
小川洋子「密やかな結晶」講談社文庫
ジョン・コナリー「失われたものたちの本」創元推理文庫
最近、浴室に文庫本やKindle Paperwhiteを持ち込むことを覚えた(覚えてしまった)ので、新しい入浴剤と石鹸が欲しい。その時読んでいる作品ごとに変えられるよう、何かふさわしいものを複数用意できれば。
読み終わった本を図書館へ返しに行くついでに買って、帰る計画を立てる。
のぼせすぎると最悪死ぬ、でも適度に長めの入浴は体重や体型の維持にも効果があるので、ずーっと湯船に浸かっているのに書籍は大活躍。
私は温泉が大好きなのに比較的早く上がってしまうのだけれど、その理由が、暇だから。入浴中でも空いている時間に何かしなければ無駄なような気分になって疲れてしまう。どう考えても病気の一種だが、本さえあればもちろん話は別。それがあるだけで、むしろ、お湯への浸かりすぎに気を配らないといけなくなる。
10/3㈫「羊飼いの寝台の下で」
途中だったサリー・クルサード「羊の人類史」を読了。私にはとてもよい本であった。
そのうちとある章では、かつて平地で用いられた移動式の羊飼い小屋について、種類ごとに説明がなされており、特に4つの車輪がついた小屋の記述が胸に刻まれた。前部には蝶番の扉、側面には雨天時でも内側から羊を監督できるようにシャッターが設けられ、中には羊飼いが夜に眠るための寝台がある。
簡素なベッドの下には……そう、これが最も私の心を捕らえたもの……すなわち「囲い檻」なる設備が備わっていたという。では何を囲う檻なのかといえば、仔羊だ。元気がなかったり、負傷したりした仔羊を屋内に置いておくための、保護領域。
これが、小屋の中のどこかではなくて羊飼いの寝台の下部にある。
あまりにも素晴らしいので頭がくらくらした。囲い檻!
私もそこに入りたい。潜り込みたい。草を食んでいる最中、岩にでもつまづいて脚を折るなり何なりし、傷に優しく軟膏を塗られ、さらに白樺の樹皮を上から巻いてもらおう。痛くはない。ともかく、怪我をしさえすれば魅惑の囲い檻に入れてもらえるのだから。
狭い空間にうずくまる。外がすっかり暗くなると、いつも自分たちを見守ってくれている羊飼いが寝台に横たわる音がして、やがてこの上なく死に近い静謐な寝息が耳に届く。そこで、脚の折れた自分は、世界のどこにいるよりも安心して眠ることができる。
薄目になってベッドの下からそっと移動式小屋の内部を観察した。折り畳み式テーブル、小型の鉄ストーブ、医薬品も一緒に収められた食器棚。ウイスキーの瓶が1本。明日になったらあれを数滴、舐めさせてはもらえないだろうか? 傷に効くかもしれないと切実に訴えて。
人間の意識を取り戻してから自分の布団に寝転がって寝返りを打ち、枕の向こうにジッ……と耳を澄ますと、下で仔羊が身じろぎをする音が聞こえるような気がする。白い巻き毛に覆われた体躯が、床に触れる。その音を捉えるのに最適な夜だった。朝になったら雨が降っている、とはとても信じられない真夜中の天気。
今日買った本は、伊井圭「啄木鳥探偵處」創元推理文庫。
10/4㈬「夜に住まうことができれば」
まほやく(魔法使いの約束)のオーケストラコンサート、チケットが当選したので着て行ける服を買おうと思った。できればコートとマフラー、タイツさえあれば12月の寒気でも耐えられそうな素材のワンピースで、気に入った意匠のものが見つかるといい。最近腕時計も欲しくなって困っている。
ところで、真夜中の特定の時間に目が覚めてしまうのは、どういう要因で引き起こされている現象なのだろう。人によって異なるので調べてみても仕方なく、きちんと自分の状態を鑑みないと分からない。
決まった時間に布団に入ったら、そのまま決まった時間まで眠れて、さらに著しい困難を覚えることなく起床できる……果たしてそんな日は来るんだろうか。なんとなく来ない気がした。
この前も「外に出よう」と決意し、どこへ行くかもきちんと考えていたのに、まったく体が動かず起きられない日があった。そうして夜になると自己嫌悪がひどくなる。起きてさえいればあれもできたし、これもできたのに、と虚しい感じが溢れてしまって救えない。
どう行動を調整してみても眠れない日と寝すぎてしまう日が出てきて、一定の時間よりも早く目が覚めてしまうと、鬱々としてくる。朝日を浴びると世界を呪いたくなってしまう。習慣化されればこれも健康上よいものになるのだろうか、何というかとても信じられないけれど。夜に起きているとどこまでも集中できるのに、頑張って早く寝て、少しでも早い時間に覚醒しようとすると、そこからもう1日中だるいときもある。
うまく言えないのだけれど、朝の時間帯はなぜなのか、ずっと気分が悪い。
さらに、怖いことを沢山考えてしまう。だから苦手。
夏目鏡子さん(漱石の妻)も「漱石の思い出」の中で私と似たようなことを述べている。朝型と夜型の人間は遺伝子に差異があるとする説も有力らしいし、やはり活動が得意な時間帯と向かない時間帯、というのはあるのだろう。世間に合わせやすいのは朝型かもしれないがどうしようもない。
図書館で手に取った小森陽一「漱石を読みなおす」(岩波現代文庫)は偏りが少なくて、さらに著者の語り口に作品への誠実さが現れていて、同じ漱石好きとして楽しく読める本だった。新たになるほどと思えた示唆もいろいろある。名前の話など。
そう、再来週にピーター・S・ビーグル「旅立ちのスーズ」が発売されたら同時に、その前作にあたる「最後のユニコーン」の電子版を買おう。これらは2冊一緒に読んでしまいたい。
10/5㈭「バス」
時刻表と呼ばれる小さな看板の前に並んでいると、やがて横に長い大型の車が来る。
それには料金を払うと乗ることができ、乗客は硬貨で支払いをするものもいれば、電子決済のカードを用いるものもいた。座席はだいたい後ろの方から埋まっていく。みんな黙々と、まるで遠い土地に住む知人の慰問に赴くような沈痛さを全身から醸し出しているが、ほとんどの人たちはただ家に帰るだけなのだ。
満員になった車は発車した。アナウンスの声は、低く、窓や壁や床をびりびりと震わせる。それは乗客に、船が係留していた場所から広い海原に漕ぎ出す際のような不安を抱かせる。「つぎ とまります」という言葉の「つぎ」とは、どこだろう。もしかしたらバス停のことではなくて、どこかこことは異なる場所にある、とても怖いところを指しているのかもしれない。
私は運転席に比較的近い側の座席に腰掛けて、自分の左斜め前方、ほとんど横と言ってもいいところに立っている誰かの靴を眺めていた。
そしておや、ずいぶんと大きな靴だな、と思う。
黒い革靴で、つま先の形はどちらかというと角ばっていた。何の変哲もない意匠の靴だ。ただ、規格外の大きさだけが印象に残る。顔を上げることはしない。私の視線も顔も、手元の本へと向けられていて、視界の端にはかろうじて、右側の窓の低い位置から外の様子が見えた。日没の時間に空がまだ明るく、橙や蒼に色づいていると、手前にある雲は灰色になって煙のようだった。
大きな靴の持ち主は頭上でなにやらブツブツと呪文を唱えている。無意識に聞き取ろうとする意識を押しとどめて、文字の列を追う。もしも意味を解したら頭がおかしくなってしまうかもしれない。何かの間違いで人間のバスに入り込んできた、まったく別の存在が近くに立っていることを実感した。
祈るような気持ちでいると、やがて薬局の前の停留所で、その靴は下車していった。少しも足音を立てることはなかった。ようやく顔を上げると保護者の腕に抱かれた幼子がいて、その肩に丸い顔を載せながら、不意にこちらを見て「エヘヘ」と笑った。なんて恐ろしい。
家に帰るのは命がけの行為。街には、いろいろなものがいるから。
10/6㈮「幸福よりも、満足よりも」
すすめられて「はじ繭2023summer」から入ったTRUMPシリーズのうち、ミュージカルを連続で視聴した。新旧リリウム、マリーゴールド、ヴェラキッカ。感想は後日、個別の記事にて。
鑑賞しながら贅沢に爪を切っていた。
爪をいつもより短めの長さに整えると、驚くほどキーボードを打ちやすい。あまりにも快適なのでびっくりした。本当はあと1~2ミリ程度指先から出るくらいが見た目にはいいのだけれど、色々と作業がしやすいので、しばらくはこのままでいると思う。
それにしても生活を愛することができず、何もしていないでいるという状態に耐えられないのだが、身近な人間と話すとそれが色々な側面から浮き彫りになる。気が付かされるのは、意義や意味、価値、そういう「どうして自分が今の世に生きなければならないのか」という幻想を半ば脅迫的に求めていた方が、呼吸がしやすい人間も中にはいるということ……。
例えば、何もせずともそこに存在してただ息をし淡々と心安く生活を送っているだけでよいのだ、と、言われても、楽になれるどころか苦しいだけだった。退屈でとにかくつまらなくてつまらなくって仕方がなかった。
私の周囲にはそういう人が多い。
そして、そういう退屈からどうにかして逃れようと、焦燥に突き動かされている人達が私は好き。世間がどれほど滑稽だと判断しても。お前に価値はあるのか、と友人たちに鋭く問われることは、すなわち存在を認められること。
単に娯楽に耽溺するにしたって、どんなものを見ても、聞いても、体感しても無心にはならない。優れたものや好きなものに触れると、次は自分自身で描きたい風景がどんどん頭に浮かんでくる。それらを漠然とした状態から、少しずつでも文字の形にして「現実」に変えて、記録していかないとつまらない。私という個が何もせず生きることと、そんな状態をもうひとりの私の視点から観察することがつまらない。
記録、記録、記録。大好きなのは記録することと記録されたもの。
人間が無意味なことは知っている。各々が勝手に何かを見出しているだけで、そこに何かがあるわけではない。だから必死で生存価値を追い求める人を愛すると同時に、実際には存在しない「物語に登場する木こり」に対しても、ときどき強い思いを向けることになる。そういうのもいいな、と思うのは本心だ。でも……。
ただ生きること、生活そのものを愛せればきっと人間は「幸福」になれるだろう。寝て起きて、それだけに満足する。だが、私は実は幸福になりたいのではなくて、常に満足することがないまま、何かし続けていたいのだとも思う。もしも満足したら、それは死に似ていて、心の何かが永劫に停滞し「終わって」しまうから。
今日も100均で買った大きめのノートに架空の景色や、かつて見た情景や、感情を書き出していた。それらを読み返したり書き直したりするあいだ、やはり楽しかった。また明日、明後日、絶えずそこに書き足されるだろう。きちんと生きている。記録がされなければ、何者も生きていたことにはならない。
少しも痕跡が残らなければ存在しないのと同じ。
10/7㈯「砂抜き」
食べ物を口に入れて、咀嚼したとき、まれにとても嫌な音がする場合がある。
実際、何が混じってしまっていたのかを確かめることはない。すぐに吐き出して捨ててしまうから。多分その音の出処は様々だが、まさに砂、としか形容しようのないじゃりじゃりした感触は共通していて、歯に当たれば一瞬で脳に伝わり全ての食欲を奪う。
砂に似た食感の異物は必ずしも料理全体を蝕んでいるわけではないのに、混入していた箇所だけでなく、残りの部分までも食べようとする気がすっかり失せてしまうのは、人間に備わった危機を避けたがる習性のあらわれなんだろうか。
この後に尾を引く独特の不快さは、食事だけではなく他の物事……例えば自分の情動や心境などを観察していても、ときどき得られてしまう。
何かを楽しんでいる最中に入る邪魔。身体に干渉するのではなくて、思考の方に作用する要素とか。私はおいしいかき氷に舌鼓を打っているとき、目の前で「かき氷はまずい」「馬鹿舌」などと述べられたらすごく嫌だ。そういう場合、あ、砂を詰められた、と判断する。
食べ物に混入した砂と同じで嫌な感触が残るから、何かを読んでいたなら続きを読むのが苦痛になるし、何かを視聴していたのなら、続きを見る気持ちが萎えてしまう。まったく無視して気にしないということができない。忘れることもできない。ただ、蓄積されていく。延々と。
私は貝の砂抜きを思い出す。
アサリやハマグリなどを調理する前に、しばらく水に漬けて砂を除去する行為。
※書いている途中で気絶したのでこの日はここまで
10/8㈰「カモのブローチ」
本当のところ、自分が果たして何を感じ、どのように思っているのかを、自分自身では『確かめる』ことができない。恐ろしいものだ。私は誰で。どんな人間なのか。常に、私から見た『私なる対象』を前に尋ねる必要が生じていて、けれど、根本的に確認の達成は不可能である……という状況。
以前は、心を持てば問いが始まるのだと思っていた。しばらく経ってから、心の在処やその存在の有無すら、どんな方法を用いたとしても確かめられないのだと理解して嘆息した。私には心が何か分からないし、他に分かる人間もこの世にはいない。ただ、問いだけがあらゆる事物に織り込まれるようにして、不可分な状態で在る。
夕方、月曜日に買っておいた小川洋子の小説「密やかな結晶」を読み終わった。
読んで私が考えたのは、1匹のカモのおはなし。机の上に置いてある、カモ(オスのマガモ)の形をしたブローチが、この部屋に流れ着くまで辿ってきた道筋の物語。
——水辺から離れた山道を歩いていたら、瀕死のカモが大樹の根元にうずくまっていた。
大きな怪我のせいでその命はすでに失われようとしている。血が流され、小さな黒い瞳が乾き、瞼は永劫に閉じられようとしている。そのおはなしの中だと自分には少しの力があり、カモの傷を癒すことはできたけれど、どうやら延命を試みるには遅すぎたようだった。さらに厳しい規則で、死んでしまったものを蘇生させるのは禁じられている。
そこで私は完全に臓器や精神の活動が停止する前に、カモをブローチへと変容させることにした。
もたらされた結果として鼓動の音は消え、呼吸の息吹も感じられはしないけれど、カモの命そのものは失われるのではなくて形を異にして世界に固定された。
ブローチになってもその羽毛のツヤは、釉薬の澄んだきらめきとして受け継がれていた。粘土で象った輪郭は怪我をしていた状態よりも幾分かふっくらとして、細い首はうなだれることなく、しゃんと芯をもって頭が前の方を向いている。首の白い輪には忠実さが宿っていた。黄色いくちばしには、誇りが宿っていた。
自分がそれを身に着けて色々な場所に赴くほど、カモは多くの旅をすることになる。
黒い眼の奥には、常に新しい風景が存在しない網膜から反転して、脳ではなく魂に映し出されるだろう。私は不安な時に、カモのブローチを指で触り、何度も撫でさする。感触が記憶に残りさえすれば永久に失われないのだと確かめように、むしろ願うようにして、粘土の羽を触っている。
★-----★-----★-----★-----★