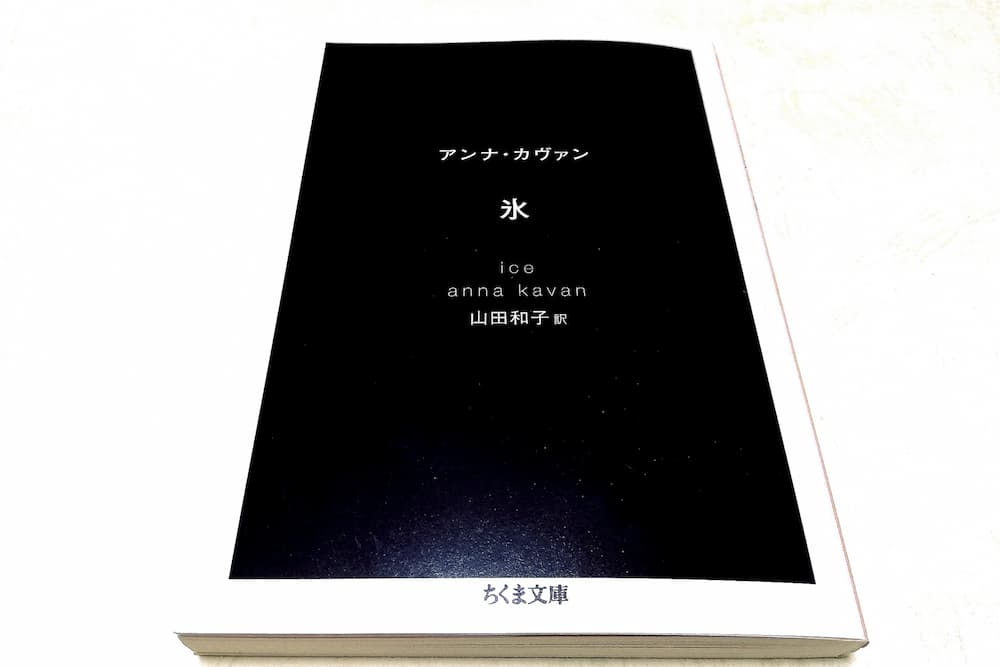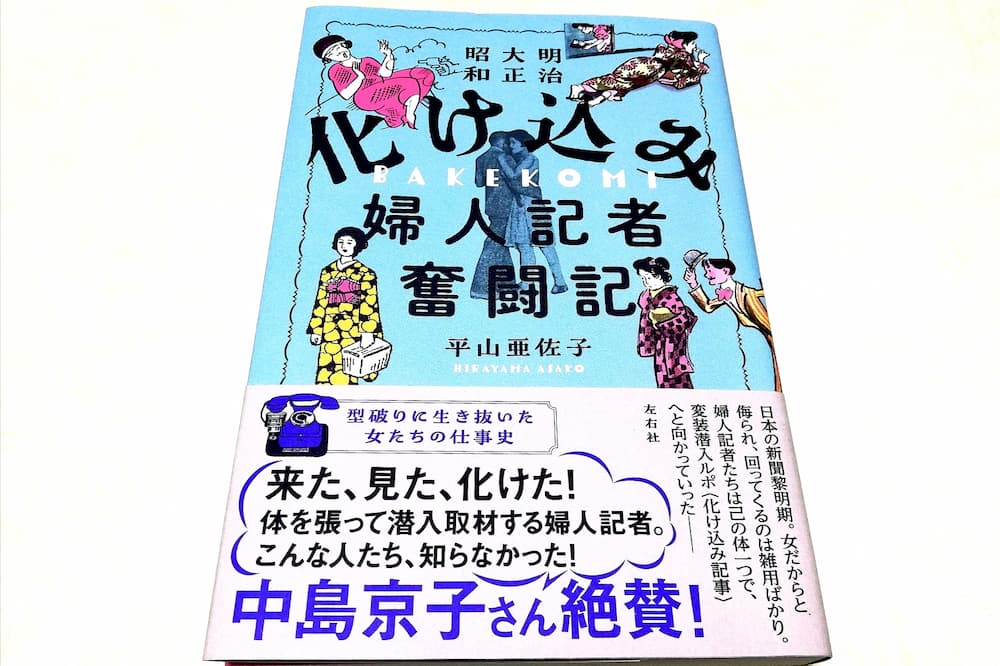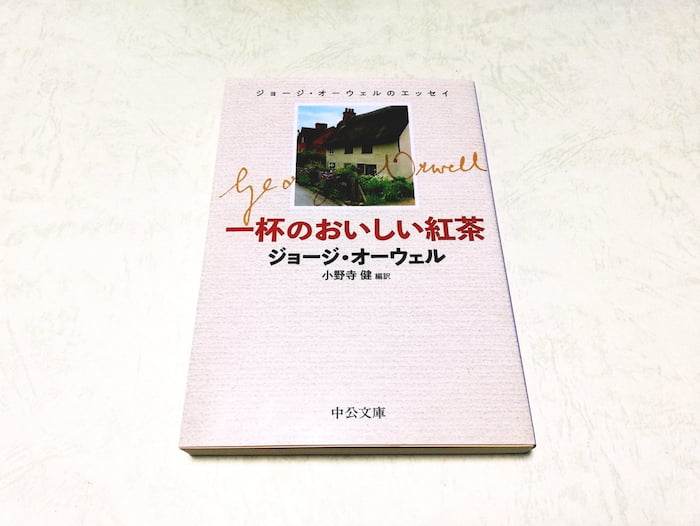物語の中には単に美味しそうなだけではなく、妙に気になる、あるいは場面や状況も含めて印象的に描かれた食べ物や飲み物がよくある。
そういう、本の中に出てくる食べ物や、読んでいてお腹が空いてしまう箇所の話。
※原文のみの読解で日本語版は手元にありませんので、ここに載せている台詞の訳などは基本、私が個人的に行ったものです。
前回:
先日手に取った《The Forgotten Beasts of Eld(邦題:妖女サイベルの呼び声)》の著者、パトリシア・A・マキリップ。世界、情景の繊細な描写や、魔法の背景に透ける考え方が自分の好みなので、他の作品も沢山手に取りたいと思っているところ。
今回の《Od Magic(オドの魔法学校)》も良かった。絶版の日本語版は手に入らなかったので原著の電子書籍を購入し……。
タイトルからも分かるようにボーム「オズの魔法使い」のオマージュがそこかしこに見られるのも楽しい。「サイベル」よりも全体的な調子は軽く、どこかコメディタッチな群像劇でありながら、未知のものを恐れて遠ざける心理と向き合う主題は一貫していて重みもあった。「既存の枠から外れたもの」への恐怖が、時に人の目を曇らせる、と言っている。
そして「オド」は何より、ヌミス王国の都ケリオールに存在する区画のひとつ、トワイライト・クォーター(Twilight Quarter, 原島文世氏訳だと「歓楽街《黄昏区》」となっている)の描かれ方が最高に魅力的だった。
地平線の向こうに太陽が沈んでから通りに灯りが点って、さっきまでいなかった人達が路地を闊歩する。
不意に商店の扉が開いたら営業開始の合図で。
複雑な香辛料の香り、また出来立てのパンや、火で焼かれる肉やら玉ねぎやらの匂いがふわふわ漂ってきたり、音楽が聞こえてきたり……目や耳や鼻がいくつあっても足りないだろう。
Smells of meat and onions sizzling on flames, freshly baked bread, kettles of hot soup mingled with the market scents of fruits and animals and exotic spices.
(McKillip, Patricia A.《Od Magic (English Edition)》p.39 Orion. Kindle版)
切実にこの区画を歩きたい。
-
オリーブの実(種あり)
川を見下ろせる屋敷に住んでいる歴史学者、セタ(Ceta)。
北部領主の娘である彼女は、あまり意に沿わない政略結婚の伴侶が若くして亡くなってからというもの、再婚はせずに独身を貫き通している。そうしてひょんなことから縁を結んだのは魔法学校の教師、ヤール(Yar)だった。
彼らはときどき、夕方になるとセタの家に集ってその日あった事柄を話すなどしながら、心安らぐ時間を過ごしていた。書物や巻物に囲まれ、古いカーペットの上で口にしている食べ物の数々(スパイスで味付けされた肉、塩漬けの野菜、平べったいパンの上に乗ったチーズ!)はこの上なく食欲をそそるが、なかでもたったひと粒のオリーブが持つ輝きは計り知れない。
セタがその指先に摘まむのは、数多ある中でも「最もふっくらとしたオリーブ」で。
She picked out the plumpest olive, nibbled around its seed.
Yar leaned back, watching a gnat tangle itself in her drifting hair. ‘Is there a point,’ he inquired mildly, ‘to your tale?’
She spat the olive pit into her hand and tossed it out the window.
(McKillip, Patricia A.《Od Magic (English Edition)》p.30 Orion. Kindle版)
種が取り除かれていないオリーブの粒。
それをひとつ摘まみ上げ、果肉を少しずつ齧ったあとは種を窓から川へと投げてしまう。川面には夕方のケリオールの街、そこから発される光が映っていて、流れとともに細かく揺らいでいた。さらに高台から眺める空の方は黄昏の、ラベンダーを連想させる紫に染まっている。
一日の仕事をほとんど終えて味わうひと粒のオリーブの実、どれほど滋味に溢れているだろうと想像せずにはいられなかった。
-
串刺し羊肉
ヌミス王国の北、田舎の村からはるばる王都にやってきたブレンダン・ヴェッチ(Brenden Vetch)。
彼は魔法学校を創設した巨人〈オド〉に勧誘されて、そこで庭師を勤めることになっていた。物語の開始時点で彼が背負っていたものは重く、悲しい。村を襲った疫病で両親を失い、弟は旅立ち、さらに恋人メリッド(Meryd)にも去られてしまっていた。特に恋人との離別は、ブレンダンがあまりにも人間と接することに無頓着かつ不得手だったため、自分は彼に必要がないのだと思われてしまった結果。
実はブレンダンの能力には秘密があるのだが、それを示す一端が、植物などの自然の声を聴くことができるというもの。しかしそんな彼なので、人間が多くいる場所ではどこか所在なさそうにしていたり、静かな場所を心の底で求めたりしていた。
あるとき、街に下りた彼は「歓楽街《黄昏区》」へと向かう。見慣れぬ植物の名を知る手掛かりを探してのことで、途中の屋台では買い食いをした。
Wye had given him some money for his work; he spent a coin on mutton rolled around cloves of garlic and roasted on a skewer, another on a cup of ale. He ate watching a knife-thrower extinguish candles with his blades.
(McKillip, Patricia A.《Od Magic (English Edition)》p.151-152 Orion. Kindle版)
1枚のコインと引き換えに得たのは、ニンニクの欠片を羊肉で巻いて串焼きにしたものと、コップ一杯のエール。
加えてそれを味わいながら見ていたものとは、黄昏区で行われていたナイフ投げの出し物だった。松明の光で周辺は照らされ、夜は深まり、黒く閉ざされていく空と半比例するように華やかな音と色彩は門から溢れる。そして、頭上に輝く月……。
あたかも街に満ちた熱気で焼かれたかのごとき羊肉のしょっぱさと、栄養満点のニンニクの香り。火照った身体を冷やしてくれる一杯のエール。読んでいると本当にお腹が鳴るから、もう絶対夜にページを開いてはいけない。
-
巨大なトレーの上のドライフルーツ
ヌミスの現国王ガーリン(Galin)の娘、スーリズ姫(Sulys)は誰にも己の話を聞いてもらえないことに悩み、憤っていた。彼女の婚約者ヴァローレン(Valoren)でさえも、「父である王の意思とあなたの意思は同じものであるはず」などと宣う始末で手に負えない。
それに、彼女には外国出身の曾々祖母から密かに受け継いだ魔法を知る、という秘密があるのだ。
この国では規制され、認められていない魔法を彼女が使えるとヴァローレンが知れば、必ずその檻の中に彼女を押し込めようとするだろう。ヌミスでは今、魔法学校で定められたことしか生徒には教えず、好奇心や探求心を抱く余地をすべて奪っていた。
このままではいられない、と考えていたスーリズは、ヴァローレンの親戚であるセタを頼る機会を得る。少しずつ交流を深め、物語の後半では行き場をなくした彼女が、セタの家まで赴き朝食をとった。
She brooded silently, while Shera set an enormous tray laden with dense, spicy breads and cakes, dried fruit, soft cheeses, pickled eggs, and smoked fish onto a table in front of them.
(McKillip, Patricia A.《Od Magic (English Edition)》p.250 Orion. Kindle版)
小間使いのシェラ(Shera)が机に置いていったのは巨大なトレーで、おそらくセタの家ではこれが普通の朝食なのだろう。
それにしても豪華なこと……! トレーの上に「ぎっしり」という形容詞がふさわしいほどひしめいているのは、スパイス風味のパンやケーキ、ドライフルーツ、柔らかなチーズ、塩味の卵、そして魚の燻製まで。なんというご馳走か。
これらのうち、会話しながらスーリズ姫が手に取っていたのがドライフルーツだった。父王がその妻、つまりは彼女の母と死別してから変わってしまったことと、おなじように兄の性格にも変化が訪れたこと、やりきれない思いを吐露するように言葉を紡ぐ。
そんなスーリズを助けるように、セタは冷たい水を彼女のコップに注いであげた。これがまた普通の水ではなく、ミントの味と香りを移したものであるというからたまらない。
Ceta poured her a cup of cool water scented with mint; Sulys sipped it gratefully.
(McKillip, Patricia A.《Od Magic (English Edition)》p.251 Orion. Kindle版)
スーリズはありがたくそれを飲むのだった。