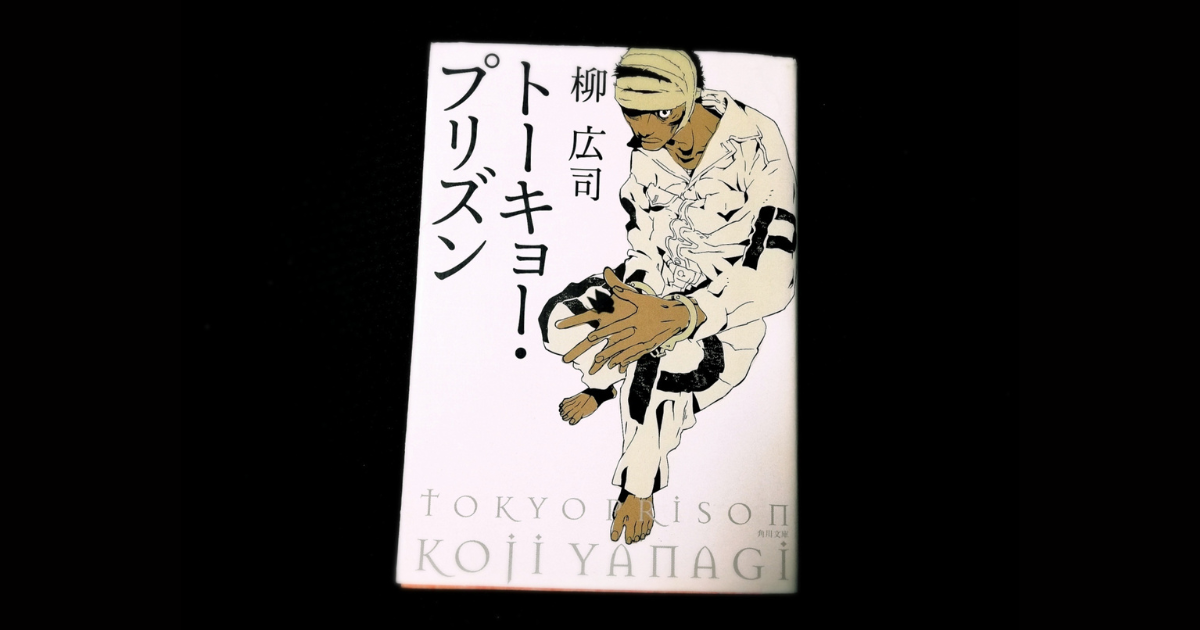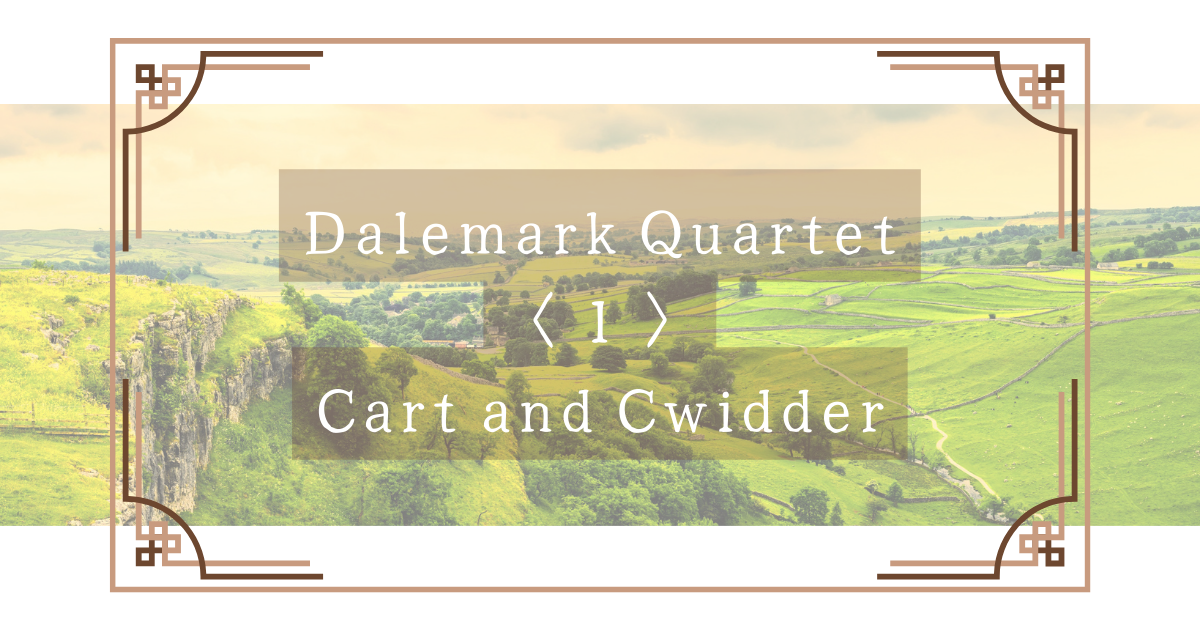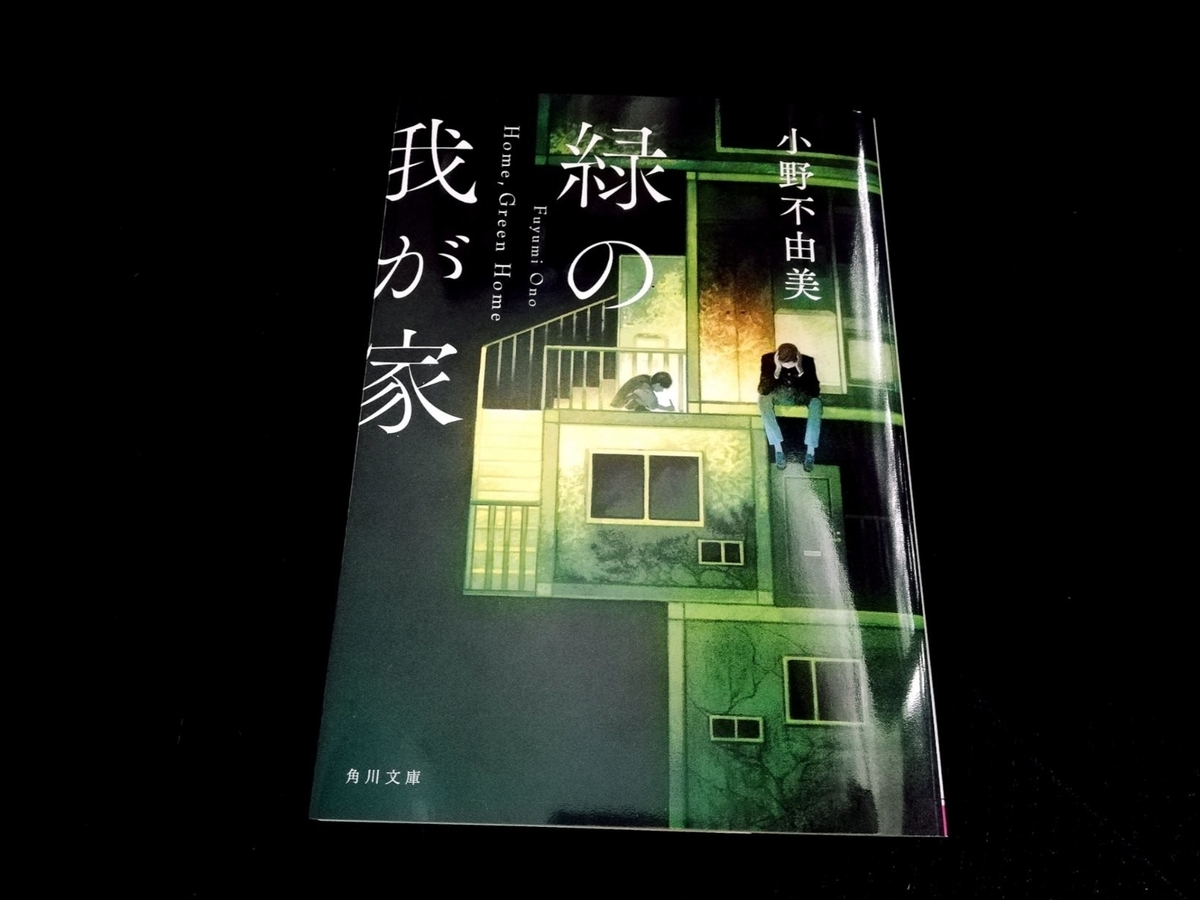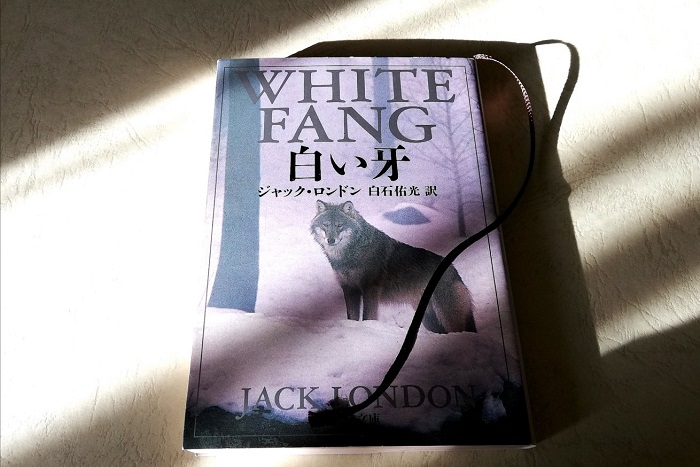Adobe Illustratorというソフトがある。
バージョン(おそらくCC 2017以降のもの)によっては、ワークスペース上でテキストボックスを作成する際、サンプル文章が自動挿入される機能がついており、実はそれに使われているのが夏目漱石の小説「草枕」だった。
この作品の冒頭は至るところで引用されているため、よく目に付く。
山路を登りながら、こう考えた。
智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.6)
そう、上の箇所は特に。
確かに印象的で共感を呼ぶことには同意するし、実際上の引用を含めた「草枕」最初の(一)の区切り(「非人情がちと強すぎたようだ。」まで)は結構きれいに独立させられるというか、作品の根幹にある要素が凝縮されてはいる。
……が、せっかく「草枕」が全体を通して大変にキレッキレで面白い文章の集積である事実を考えると、冒頭だけが切り取られて流布し、肝心の内容が知られていないのはかなり惜しい。
私がより好きなのは別の部分なので、なおさらそのように思うのかもしれない。
「草枕」が素晴らしいのは、とりわけ最後。
主人公の画工(えかき)が、あくまでも「非人情」の視点から、一定の距離を保ち観察しようと努めていた(にもかかわらず、結局かなり翻弄されてしまった)対象の女性に対して、まるで「意趣返し」のようにある台詞を言い放つところ。
漱石の他作品に登場する美禰子、藤尾、そしてお延といった魅力的な人物像に並ぶ特徴を持っているのが、この「草枕」における志保田の娘、お那美さんなのだ。
パブリックドメインの作品です。
草枕 - 夏目漱石(青空文庫)
目次:
読んで楽しい「草枕」
-
概要(仮)
そもそも「草枕」に「筋書き」は存在するだろうか?
漱石先生に尋ねれば、もしかしたら否、と返されるかもしれない。
この作品は著者本人が「『俳句的小説』である」と述べているように、いわゆる「何か一つの出来事にまつわる起承転結や、順序だった展開」というものはない。
余が嬉しいと感ずる心裏の状況には時間はあるかも知れないが、時間の流れに沿うて、逓次に展開すべき出来事の内容がない。一が去り、二が来り、二が消えて三が生まるるがために嬉しいのではない。初から窈然として同所に把住する趣で嬉しいのである。
(中略)
このムードは時間の制限を受けて、順次に進捗する出来事の助けを藉らずとも、単純に空間的なる絵画上の要件を充たしさえすれば、言語をもって描き得るものと思う。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.72-73)
反対に一般的な小説とは何か、に関する漱石自身の基本姿勢を知りたければ、別の作品「坑夫」への言及が参考になるかもしれない。それか、短編「一夜」の最後の段落なども。
筋書きのようなものがない……となれば、ここで私が勝手に「あらすじ」という言葉を使ってしまうと厳密には不適当な気がした。だって文字通りに筋はないのだから。物語というより一幅の絵であり、一篇の詩でもある、既に存在し展開されているものをいかに写すかの点に注力されている、著者が言うところの俳句的小説。
でも、主人公は具体的に何かを成したり事件に巻き込まれたりすることこそないけれど、きちんと生きて周囲の事物を見、聞いて、感じている。出掛ければ人に会うし、話すし、また風景も眺めてそれに対する所感を述べる。確かに「展開」の動きはないが、人物も自然もごく普通に動いている。
ここは「あらすじ」ではなく「概要(仮)」とさせてもらい、表面のみをなぞって、おおまかに作品を説明した気分にさせてもらおう。漱石先生……すみませんが、よろしくお願いします。
❀ ❀ ❀
画工の主人公は、那古井(なこい)の温泉地にしばらく逗留するつもりで山を越えて来た。
ちなみに那古井のモデルは熊本県にある小天温泉だと言われており、地名としては架空のものだが、作品にちなんだ「那古井館」という老舗旅館(明治元年創業)が小天に存在する。
そして「草枕」作中で主人公が赴いた志保田という宿屋の描写、こちらは同じ小天温泉で漱石自身も宿泊した、前田家(前田案山子)別邸のつくりと一致するようだった。半地下に掘り込んで設けられた浴場は、当時には珍しくセメント造りであったようで、建物としても見どころがある。見学したい……閑話休題。
「また寝ていらっしゃるか、昨夕は御迷惑で御座んしたろう。何返も御邪魔をして、ほほほほ」と笑う。臆した景色も、隠す景色も――恥ずる景色は無論ない。ただこちらが先を越されたのみである。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.48)
温泉地で画工は、ひとりの謎めいた女性に出会う。それが志保田の娘・那美だった。
彼女はかつて2人の男から妻にと望まれ、結局は親が決めた城下の物持ちの方へと嫁に行ったものの、折悪しく結婚相手の勤めていた銀行が潰れてしまったらしい。それで出戻りを果たしたわけなのだが、周囲からはそれが薄情だと言われたり、あるいは奇矯な言動のために「気狂い」などと陰口を叩かれる場面もあったよう。
主人公はこのあたりの詳しい事情にあえて突っ込もうとせず、できるだけ温泉地滞在中に触れるものを他人事と捉え、後述する「非人情」の目で観察しようとしている。ゆえに読者にも限られた情報しか開示されないのが、むしろ味になっているのだった。
さて、深入りはしないと意気込んではいるものの、画工の余はお那美さんに情緒を揺さぶられてばかり。
夜に歌っている声を聞いたり、作った俳句のノートを広げて置いておいたら脇に新しく句を追加されたり……果ては無為に絢爛な振袖を着て、刃物を持ち、宿の廊下を芝居のようにスルスル歩いているのを目撃したりと、枚挙にいとまがない。
臆することを知らず、打てば響く会話のできる回転の速い頭で、常人ならばしないようなことを易々とやってのける気風がお那美さんにはあった。極めつけに「私が身を投げて川に浮いているところ(その安らかな死に顔)を絵にしてみて下さいな」と画工に告げ、びっくりしている顔を見て、彼女はたいそう喜ぶ……。
憐れは神の知らぬ情で、しかも神にもっとも近き人間の情である。
御那美さんの表情のうちにはこの憐れの念が少しもあらわれておらぬ。そこが物足らぬのである。ある咄嗟の衝動で、この情があの女の眉宇にひらめいた瞬時に、わが画は成就するであろう。しかし――いつそれが見られるか解らない。
あの女の顔に普段充満しているものは、人を馬鹿にする微笑と、勝とう、勝とうと焦る八の字のみである。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.112)
ある日、主人公は寺の裏道から行ける「鏡が池」へ赴いた。紅椿の落ちる凄艶な水面を目にして、例えば美しいお那美さんをモデルにした人物を(ミレイの「オフィーリア」さながら)ここへ描き込んだら、さぞ面白い絵が描けるだろうと空想する。
だが、どんな表情をさせたらよいのかが問題だ。
嫉妬でも、怒りでも、恨みでもない。最もふさわしそうな「憐憫」の感情は一体いつ、どこでなら彼女の顔に浮かぶのか?
その疑問が最後に氷解する。
❀ ❀ ❀
「草枕」の後半、那美の従兄弟・久一という青年が徴兵されたのを見送るため、山を越えるより楽な川船で鉄道駅(停車場・ステーション)まで足を延ばした一行。
駅名が吉田とされているが、これも那古井と同じく架空の名前で、もしかしたら上熊本駅の前身であった「池田駅」あたりが想定されていたのかもしれない。なら、川というのは井芹川だろうか。そんな気がするが真相は不明。
そこでとある人物(風貌から「野武士」と描写される。実はお那美さんの元夫)が発車間際の汽車から顔を出し、彼女と目を合わせた。どういうわけか久一と同じ便で那古井を去るところだったのだ。瞬間、初めて那美は「憐れ」を面に出し、結果として画工の心には明らかに「意趣返し」の気持ちが浮かんだと思う。
そういう色が台詞に乗っている。
あれほど自分を意のままに翻弄してきた勝気な女性が、平たく言えば相手を負かすのではなく、ある意味では反対に何かを挫かれた時の表情をようやく目の当たりにすることができたのだから、当然かもしれない。
「それだ! それだ! それが出れば画になりますよ」と余は那美さんの肩を叩きながら小声に云った。余が胸中の画面はこの咄嗟の際に成就したのである。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.154)
画工として、最後に非人情な立場(つまり、相手をあくまでも「描写する対象」として観察できる心境)を取り戻せた主人公の顔に浮かんでいたのは、おそらくかつて彼女が見せたのと同じような、「ああ、わたしの勝ちですね」……という表情であったに違いない。
さぞ悔しかったことだろう。ずっと、相手の方が明らかに精神的優位に立っていた状況は。
コミュニケーションにおける優劣と勝敗の関係は、この「草枕」では少々コミカルに描かれているが、後の「明暗」に至ってより深刻かつ根本的な問いの喚起へと繋げられる。
そちらも気になれば読んでみてほしい。
-
非人情の視点とは
「すると不人情な惚れ方をするのが画工なんですね」
「不人情じゃありません。非人情な惚れ方をするんです。小説も非人情で読むから、筋なんかどうでもいいんです。こうして、御籤を引くように、ぱっと開けて、開いた所を、漫然と読んでるのが面白いんです」
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.100)
これまで何度も登場した言葉「非人情」は「草枕」の主題であるとも言ってよい要素だが、具体的にそれはどういったもので、また、どんな状態を指しているのだろうか。
留意してもらいたいのは、これと「不人情」というのは全く別の意味を持つ言葉である点。例えば何かに対して「人情味がない」と表現するとき、それが指すのはおそらく不人情寄りのもので、どちらかというと「情に欠けた、思いやりのないさま」を形容しているはず。
だが「非人情」はそうではない。
もはや現実にある人間の感情や事情、それらの一切を介在させず考慮もせずに物事を観察するとき、その境地に至れる。作中の文章を引くならまず冒頭のこのあたりか。
こう山の中へ来て自然の景物に接すれば、見るものも聞くものも面白い。面白いだけで別段の苦しみも起らぬ。
(中略)
しかし苦しみのないのはなぜだろう。ただこの景色を一幅の画として観、一巻の詩として読むからである。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.10-11)
そして、以下のように続く。
これがわかるためには、わかるだけの余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ芝居は観て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げている。見たり読んだりする間だけは詩人である。
それすら、普通の芝居や小説では人情を免れぬ。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.11)
要するに、周囲で起こることや出会うものをことごとく他人事として捉え、一枚の膜を隔てて、直接関係のないものとして世界を見ること。
その膜の向こうに何が展開していようと自分には影響を及ぼさない、額縁の中の世界を覗くように、あるいは観客として舞台の演目などを鑑賞するように、常に第三者として接する状態。
では同化(感情移入)は……というと、これもしない。少なくともしないように努める。仮にキャンバス上でどんな人間模様が繰り広げられていようと、人間の情緒・精神をいたずらに活動させるようなものとは、徹底的に距離をとるのが非人情のやり方である。
自分のことのように受け止めてしまったら、物事を単純に楽しめなくなるからだ。
苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりは人の世につきものだ。余も三十年の間それを仕通して、飽々した。飽き飽きした上に芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては大変だ。
余が欲する詩はそんな世間的の人情を鼓舞するようなものではない。俗念を放棄して、しばらくでも塵界を離れた心持ちになれる詩である。いくら傑作でも人情を離れた芝居はない、理非を絶した小説は少かろう。どこまでも世間を出る事が出来ぬのが彼らの特色である。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.11-22)
当記事の概要(仮)で言及したように、温泉地逗留中はとにかく非人情を徹底し「安全地帯にいよう」と試みる主人公の前に立ちはだかった存在が、まさにお那美さんなのであった。
だからこそ、最後の台詞にあの感情が乗せられるのである。
そして読み手の私は那美のような登場人物が大好きなのだった。
-
心躍る描写
筋書きに重きが置かれないというのなら、なおさら注目したいのが作品に登場する各要素、人や物、それらを描写する言葉の面白さ。
しっとりとした「文鳥」の感触とはまた異なる趣がある、漱石の巧みな(時に笑える)筆致を味わおう。
文明の申し子たち
1. カメラ
ただおのが住む世を、かく観じ得て、霊台方寸のカメラに澆季溷濁(ぎょうきこんだく)の俗界を清くうららかに収め得れば足る。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.6-7)
文芸雑誌「新小説」に「草枕」が発表されたのは、明治39(1906)年9月のこと。
となると文中にカメラという道具が登場するのは必然的ではあるのだが、下に引用した「心のカメラ」などの言い回しは、所によっては現代でも通用するように思えるから興味深い。
実際、過去に私も使ったことがある気がする。心のカメラに収めた、とかなんとか……。
余の席からは婆さんの顔がほとんど真むきに見えたから、ああうつくしいと思った時に、その表情はぴしゃりと心のカメラへ焼き付いてしまった。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.18)
本棚にあった「世界写真史(美術出版社)」のページをめくってみた。
1960~70年代に日本を訪れ、幕末・維新期の風景や文化風俗を撮影した人物にフェリーチェ・ベアトがいる。それの影響を受けて、日本の写真家も外国人向けの「横浜写真」を作るなど、当初は主に外国人向けの観光産業として発展していたらしい。
そして文久2(1862)年、下岡蓮杖が横浜で、また上野彦馬が長崎で、初めて写真の営業スタジオを開始。英単語"photography"の訳語として「写真」が定着したのもこの頃だったというから、そこから数十年を経る中で、徐々にカメラという語も一般に使われるようになったのだろう。
草枕に登場する表現「心のカメラ」はその延長線上にある。
2. 懐中時計(袂時計)
括り枕のしたから、袂時計を出して見ると、一時十分過ぎである。再び枕の下へ押し込んで考え出した。よもや化物ではあるまい。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.32)
懐中時計は他の作品、例えば「虞美人草」などでも「恩賜の銀時計」が印象的なアイテムとして使われたのに加えて、漱石本人にとっても身近なものだったに違いない。どこへ行くのにも持ち歩いていた様子が、随筆などから伺える。
近代日本で定時法に基づいた西洋時計が普及したきっかけは、まず明治5(1872)年の改暦を受けてその実用化が促進されたのがひとつと、重ねて明治19(1886)年に発せられた「本初子午線の勅令」が決定的だった。
非人情を追求しに幽玄の雰囲気漂う那古井の温泉へ来たのに、結局は、近代的時間秩序に紐づけられた懐中時計を持参しないと不都合な主人公の姿は興味深い。
まあ私達もそうだろう。癒しを求めて赴いた遠出の目的地であっても、そこで一度も時計を見ない状況……というのは、もはや考えられない。
何にしてもなかなか寝られない。枕の下にある時計までがちくちく口をきく。
今まで懐中時計の音の気になった事はないが、今夜に限って、さあ考えろ、さあ考えろと催促するごとく、寝るな寝るなと忠告するごとく口をきく。怪しからん。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.32)
3. 汽車
上のふたつに続いて、作品の最後に登場する点でもかなり象徴的なのが汽車の存在。
温泉逗留中、時折耳に入る戦争の話題を除いて、那古井と外界を結び付けるものは決して多くなかった。それがここに来て「鉄道」という、文字通りにソトと地続きになった停車場の前に、主人公一行は立つ。
ちなみに日本で営業用鉄道が開業したのは明治5(1872)年(上の「懐中時計」で述べた改暦の年と一緒!)で、それが新橋停車場(後に汐留駅と改称する)と横浜駅を結ぶ区間だった。
いよいよ現実世界へ引きずり出された。汽車の見える所を現実世界と云う。
汽車ほど二十世紀の文明を代表するものはあるまい。何百と云う人間を同じ箱へ詰めて轟と通る。情け容赦はない。詰め込まれた人間は皆同程度の速力で、同一の停車場へとまって、そうして、同様に蒸気の恩沢に浴さねばならぬ。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.150)
もしも「草枕」に登場する「吉田の停車場」のモデルが池田停車場なら、ここは明治24(1891)年に設置されたものになるはずだ。前述したように、現在は「上熊本駅」になっている。
牧村健一郎「漱石と鉄道(朝日選書)」でも語られていたことだが、漱石は鉄道、ひいては文明の生み出した道具とその性質を、ある意味では憎みながらも愛していた節がある。ごく個人的にそういうところがアンデルセンとの共通点だと思っている……。
汽車の車両に乗り込む人と、ホームに留まる人とを繋ぐ何かしらの糸が、ひとたび車輪が回れば切れてしまう感覚。ましてや久一がこれから往くのは遠い戦場だという。果たして、生きて帰って来られるのかどうかも分からない。
人は汽車へ乗ると云う。余は積み込まれると云う。
人は汽車で行くと云う。余は運搬されると云う。
汽車ほど個性を軽蔑したものはない。文明はあらゆる限りの手段をつくして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの方法によってこの個性を踏み付けようとする。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.150-151)
猛烈なる髪結床
作中で主人公が髪結床(かみゆいどこ)に赴き、髭を剃ってもらう場面があるのだが、どうも親方が酒を飲んでいたらしいのに加えて手つきも乱暴だったらしく(刃物を使う職業なのに恐ろしい……)施術を受けている彼は心の中でブツクサと文句を言う。
面白いのはその文句のバリエーションで、単純に一言で「へたくそ」だと片付けてしまうことをせず、持てる語彙を駆使して心境と状況を述べるのだった。「どうです、好い心持でしょう」と親方に問われて「非常な辣腕(らつわん)だ」と返す台詞なども抱腹絶倒である。
もう初めの部分からして面白い。
彼は髪剃を揮うに当って、毫も文明の法則を解しておらん。
頬にあたる時はがりりと音がした。揉み上あげの所ではぞきりと動脈が鳴った。顋のあたりに利刃がひらめく時分にはごりごり、ごりごりと霜柱を踏みつけるような怪しい声が出た。しかも本人は日本一の手腕を有する親方をもって自任している。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.56)
ちなみに髪結床……転じて「床屋」といえば、現代では「〇〇屋」という語が放送禁止、あるいは差別用語として扱われる場合があるのをご存じだろうか。私は学生時代に知って、未だに腑に落ちていない。
何といっても祖母の職業が「床屋」で、この呼称自体身近でよく使われていたものだから、尚更そう思うのかもしれない。
上のページを読んでみると、これがたびたび議論されてきた問題であるのが分かる。閑話休題。
床屋だった私の祖母も散髪をはじめ、「草枕」で描かれた髪結床のようにお客さんの髭を剃る場面もきっとあった。できればその手際が敏腕なもので、こんな風に「猛烈な」やり方は決して採用していなかったであろう、と信じたい。
親方は垢の溜まった十本の爪を、遠慮なく、余が頭蓋骨の上に並べて、断わりもなく、前後に猛烈なる運動を開始した。
(中略)
余が頭に何十万本の髪の毛が生えているか知らんが、ありとある毛がことごとく根こぎにされて、残る地面がべた一面に蚯蚓腫にふくれ上った上、余勢が地磐を通して、骨から脳味噌まで震盪を感じたくらい烈しく、親方は余の頭を掻き廻わした。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.59)
つやつやの羊羹
漱石は甘いものが好きだった。
「大」がつくほどに好きだった。
羊羹(ようかん)もそのうちのひとつで、あるとき鏡子さん(漱石の妻)が胃病にはよくないから……といつもの棚ではなく、別の場所に羊羹を隠しておいたところ、執念深く探し続けたという証言が残っている。最終的には娘に頼んで隠し場所を教えてもらったらしいから、相当だ。
菓子皿のなかを見ると、立派な羊羹が並んでいる。
余はすべての菓子のうちでもっとも羊羹が好きだ。別段食いたくはないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。
ことに青味を帯びた煉上げ方は、玉と蝋石の雑種のようで、はなはだ見て心持ちがいい。のみならず青磁の皿に盛られた青い煉羊羹は、青磁のなかから今生れたようにつやつやして、思わず手を出して撫でて見たくなる。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.48)
そんな彼が「草枕」で描写する羊羹には魅力が詰まっている。
主人公の画工は漱石本人ではないので、引用だと「別段食いたくはない」と言っているが、実際にはこの箇所を書きながらお腹が空いていたのではなかろうか。もしかしたら、本当に食べながらペンを走らせていたかもしれない。情景ははっきりと思い浮かべられる。
この場面以外にも、後にお寺でのお茶に呼ばれて骨董が披露された際、画工は凝った意匠の硯を前にして羊羹と石の質感を重ねたのだった。
形容して見ると紫色の蒸羊羹の奥に、隠元豆を、透いて見えるほどの深さに嵌め込んだようなものである。眼と云えば一個二個でも大変に珍重される。九個と云ったら、ほとんど類はあるまい。
しかもその九個が整然と同距離に按排されて、あたかも人造のねりものと見違えらるるに至ってはもとより天下の逸品をもって許さざるを得ない。
(角川文庫「草枕」(2021) 夏目漱石 p.94)
うん、綺麗だし、硯なのにとても美味しそう……。
❀ ❀ ❀
パブリックドメイン作品なので、以下のリンクから全文が読めます。
草枕 - 夏目漱石|青空文庫
紙の書籍はこちら: