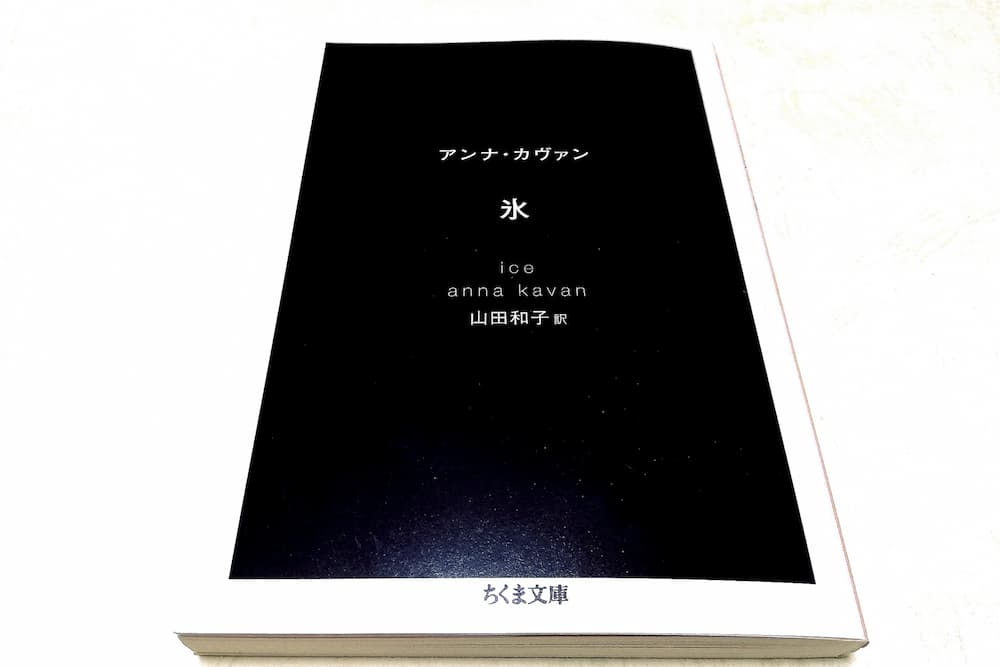
徹頭徹尾、作中の「私」にとって大切な何かが切実さを滲ませる筆致で綴られており、読者の私は主人公とそれを共有できないので、目まぐるしく移り変わる情景に置き去りにされたままページをめくる。
そう、ずっと置き去り。
何かがその人物にとって大切なことだけは伝わるが、どんな風に大切で、また、いかにしてそうなったのかは語られず、示唆もされない。
アンナ・カヴァンの《氷》(山田和子訳)を読んでいた。
白い魔にほぼ閉ざされた世界の物語といえば、カヴァンと同じ英国出身の作家・セローの「極北」が私には身近だけれど、趣は全然違う。
いや、そもそも……と《氷》の内容を回想した。
原題も"Ice"なので言葉から受ける印象は邦訳でも変わらず、それなのに読後の胸に残ったものといえば、雪原や氷山ではなく「赤道地帯のジャングルとインドリ」なのだから面白い。
「私」はジャングルで「より高き叡智、究極の真理、永遠」への扉を開きたいと望むが、結局は地上に留まる。氷と死の、超絶的な世界を選ぶ。
ここでも読者は「分かる気がする」と「一体なぜなのか」の狭間に取り残される。
生前、ヘロインを常用していた著者。
彼女自身を最後まで地上に繋ぎとめていたものは、何だっただろうか。
◇ ◇ ◇
約500文字
以下のマストドン(Masodon)に掲載した文章です。