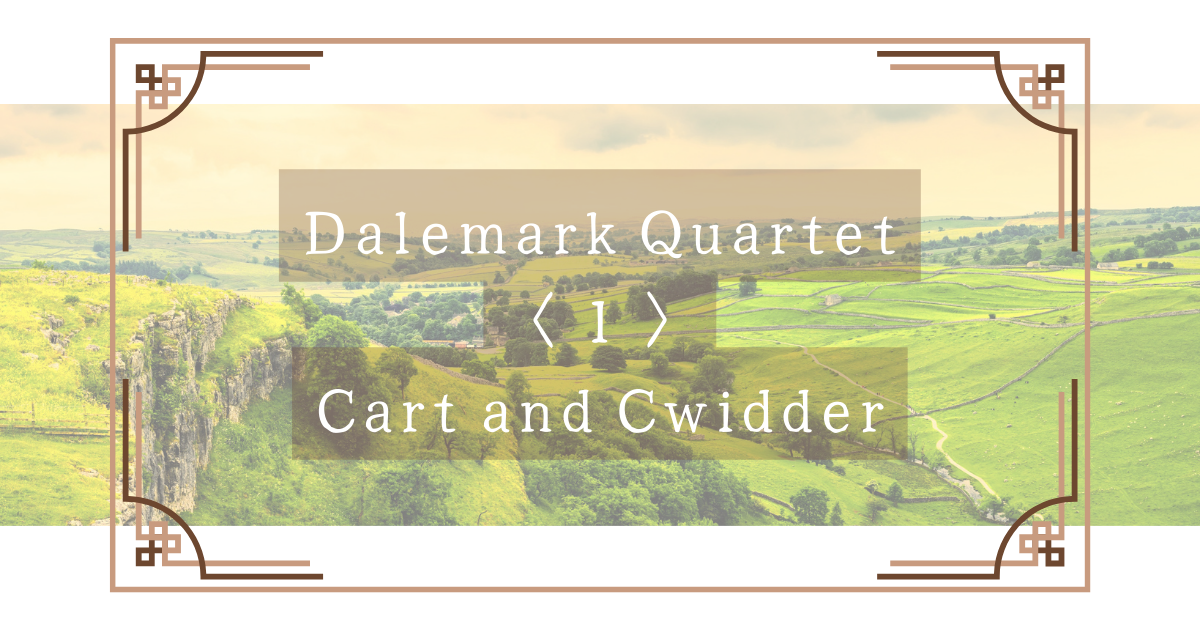
「人生みたいなものだ」そう、クレネンは言った。
「時には『この内側でいったい何が起こっているのか?』と、疑問に思うかもしれない。だが実のところ重要なのは、外からどんな風に見えるのか、そして我々がどうやって観客に見せるのか、だ。
よく覚えておきなさい」
“It’s like life,” Clennen said.
“You may wonder what goes on inside, but what matters is the look of it and the kind of performance we give. Remember that.”
(Cart and Cwidder (Dalemark Quartet) p.3 D. W. Jones Kindle版 HarperCollins)
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ著《Dalemark Quartet》4部作。
先日、その第1巻である〈Cart and Cwidder (1975)〉の原著、電子版を買って読んだ。過去に創元推理文庫から「デイルマーク王国史」として日本語訳が刊行されていたのだが、残念ながら現在は絶版で手に入らなかったので。
この巻は田村美佐子氏によって「詩人(うたびと)たちの旅」と翻訳されている。デイルマークにおける詩人(singer)とは、馬に引かせた荷車に乗って各領地を渡り歩く、吟遊詩人の呼称だった。
5人家族の次男、モリルの視点で物語は進む。
単純に歌や楽器の演奏を生業とするだけではなく、土地から土地へニュースや伝言を運ぶ役割も担っている詩人の彼らは、デイルマーク南部から北部へ至る過程の依頼で、キアランという名の人物を荷台に乗せることになり……やがて何かの陰謀に巻き込まれてしまったと知る。
複雑に絡み合う糸を解き、あるいは意図的に絡ませたり、巧みに結んだりする作風の重厚なファンタジー作品で知られるダイアナ・ウィン・ジョーンズ。
この〈Cart and Cwidder〉は4部作の序章ということもあってか、基本的に1本道だ。読者は緊張しながらもどこか安心して、物語世界に分け入っていける。たとえ起伏が大きく、あるところでは左右に曲がりくねり、ときどき遮蔽物が横たわって行く手を塞いでいる道でも。彼らの暮らす荷車(カート)の通った道筋を辿るように、歩いたり走ったりして、筋書きの先を追いかける。
原著のタイトルにあるカート(cart)ではない方の名詞、クィダー(cwidder)は、どこかマンドリンやリュートにも似たデイルマークの弦楽器。最初は弦を爪弾くのでハープのようなものかと予想していたけれど、読み進めるうちにより正確な形が掴めてきた。
その音色だけでなく、表面に施された装飾の描写も綺麗で神秘的。
The inlaid patterns on the front and arm, made of pearl and ivory and various colored woods, puzzled him by their strangeness.
(Cart and Cwidder (Dalemark Quartet) p.21 D. W. Jones Kindle版 HarperCollins)
第1巻の見どころはいくつも挙げられるが、なかでも単純なようでまったく単純ではない人間の心模様や、人物同士の関係の描写は、やはり著者の他作品と同じように際立っていると感じる。
たとえば自分が視界に入れている相手が、仮にこれまで長い時間を共に過ごしてきた、よく見知った存在であったとしても、内実までまるっきり目に映る通りであるとは限らない。
言葉にしないことは他人に聞こえないもの。それゆえ徹底して態度に出さなければ、周囲の誰かに、何かを勘付かれることもほとんどないのだ。
父、母、長男、長女、次男。
常に一家5人で旅をするモリルたちの会話や様子を見ていると、改めて家族という「他人の集まり」の面白さと奇妙さを実感させられ、冒頭に引用した「人生は観客からどう見えるか、自分がどう演じるかが重要」だというクレネン(モリルたちの父)の台詞がいっそう味わい深くなる。
今まで知らなかった家族の一面を知るのは、場合によっては恐ろしい。
特にそれが、長らく頼りにしてきた存在、例えば両親などの実情であれば尚更ではないだろうか。いかに家族集団に属し、特定の肩書きを与えられていても、それ以前に彼らが各々別の人格を持つ一個人であるのは変わらない。
人間にはさまざまな側面がある。長所と短所は表裏一体の関係にあり、どちらかだけをあげつらってその人の本質だと言い切る材料にはできないから、自体は常にややこしい様相を見せる……。
明かされた真実に衝撃を受け、悲しみ、混乱し、憤っても、困難から抜け出す糸口を探そうと奮闘するモリルや姉のブリッド、兄のダグナーの描写はとても切実で生々しい。これはその世界にある、まぎれもない現実の物語だ。ページをめくる私たちにとってはフィクションのファンタジーである、と油断していると四方八方からやられる。
現実というなら、作中の冒頭では夢見がちでぼうっとしていると皆に評されているモリルも、実のところ常に五感や第六感を働かせて誰より子細に周囲を見ているのだった。言葉や音を聞き、色を認識し、空気の手触りも匂いも感じている。
時にはそこに「あるように見えるもの」よりも、ずっと多くを。
そう、彼はしっかりと現実に目を向けているのだが、他の人間と同じような方法によって、ではない。後に同乗者のキアランがこう指摘する。
「大多数の人間に比べて6倍は意識がはっきりしてるんだよ、モリルは。
さっきから俺たちが話していたことも、一言一句漏らさずちゃんと聞いていたはずだ。そうだろ?」
“He’s about six times as awake as most people, really. I bet he heard every word we said—didn’t you, Moril?”
(Cart and Cwidder (Dalemark Quartet) p.147 D. W. Jones Kindle版 HarperCollins)
そんなモリルがクレネンから託された、特別な大きいクィダー。
遠い昔、デイルマーク最後の王であったアドンの友人にして、偉大な詩人であり、魔術師でもあったオスファメロンの遺物と伝えられている楽器。鋭敏な感覚を持つ彼は、今後、それをうまく使いこなせるようになるだろうか。また、得た力をどのように行使するのだろうか。
国全体を納める「王」が長らく不在で、現在は各領地の長が伯爵として、さらにそれを細分化した土地ごとに領主が権力を握っているデイルマーク。
4部作は第2巻の〈Drowned Ammet〉に続く。
原題だと「溺れた(沈んだ?)アメット」とでもなりそうなこの巻のタイトルは、田村美佐子氏翻訳の創元推理文庫版では「聖なる島々へ」となっていた。さて、アメットとはいったい何(あるいは誰)なのだろう。疑問とわくわくを抱いて次の巻へ!