好きな作家について
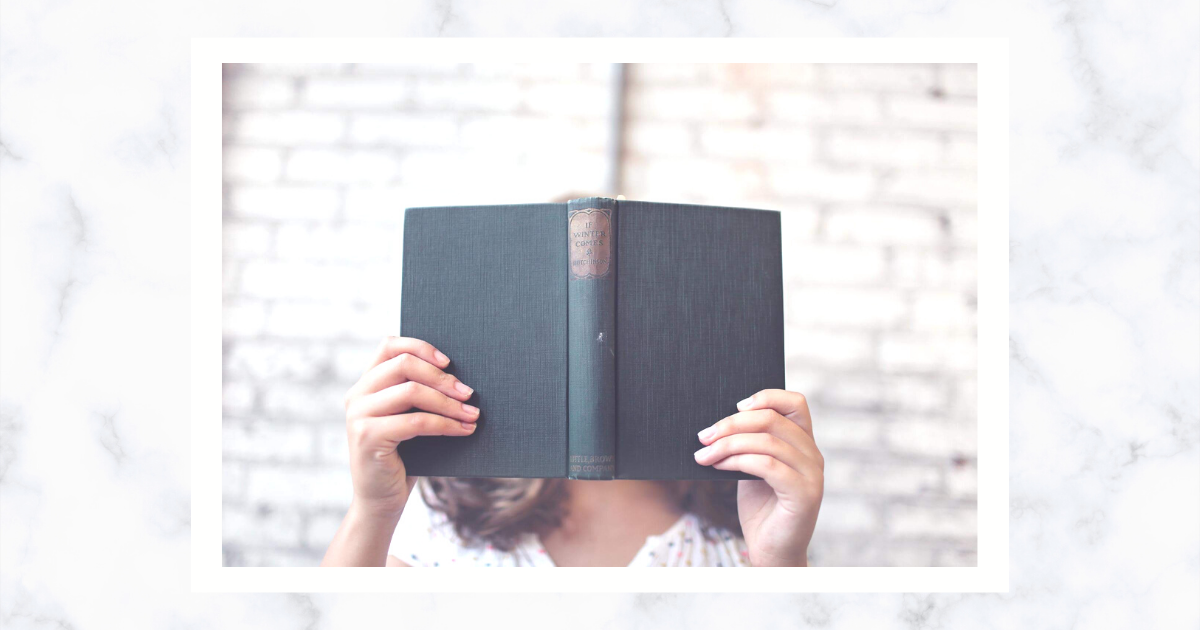
ある作家の随筆集をまた買った。最近発刊されたものと、結構古いものを一緒に。
文庫にして3冊の分量、いずれもページ数は多くなく、表現も平易なので読むのに時間はかからない。そして実際に読んでいるときよりも、その本から離れているとき、勤務を終えて会社から自宅へ向かう途中などには特に、彼女の文章がそっと肩のあたりに寄り添ってくるのがわかる。振り向くといる、みたいに。
それは心地よく安心を誘い、また氷水で心が冷やされるような、麻縄でゆるく喉元を締め上げられるのにも似た、不思議な感覚をもたらす。
私はすっかり自分自身の言葉を奪われた気分になってしまう。
彼女は存命の作家である。日本で生まれ、育ち、確かに今もどこかで生きているはずの。
調べると、私の母と同じ年齢であった。重なる時代に存在していると同時に、それだけ年月の隔たりがあるのにもかかわらず、書かれた事柄に対してどうしてここまで共感に似た思いを抱けてしまうのか、理由は分からない。
それは、現代の人間が古代から近代にかけて書かれた文章に触れて共感をおぼえるのとは、ぜんぜん本質が異なるものだ。
育った環境が違うし、学んだ分野も、母国以外で滞在していた国も、携わっている仕事もぜんぶ違う。それなのに。
まだ生きている作家の随筆にほとんど惹かれてこなかった自分にとって、彼女の作品との出会いは、月並みな表現だけれど文字通りに青天の霹靂だった。最初、たまたま小説を手に取ったら他の作品も気になり、今度はエッセイ集、と副題に記載されたものを紐解いたときの驚きといったら、とても言葉では言い表せないほどで。
冗談ではなく、もう一人の自分が確かにそこにいて、口をきいているのだと錯覚した。本当に恐ろしいものだった。
私が人生のどこかで選ばなかった方の道、彼女はそこに独りで立っていて、幅の広い河川の向こう側からひらひら手を振っている。周囲にたくさん人がいるのに、文章に関してだけは完全に孤独な場所に立ち、世界の半分に背を向けて手を振っている。
彼女も「回想」をするようだった。
黙っていたら刹那に通り過ぎ、いつかは記憶の彼方に押しやられてしまう物事や事象の中から、いくつかを傲慢とも表現できるほど丁寧に選んで、選り好みして、手のひらで掬い上げている。何らかの特権を振りかざすみたいに……。
その過程で綴られる言葉を前にして、共感に似た思いを抱き頷いているときの私は、すっかり影が希薄になる。彼女がこうだと言ったものに半ば身をゆだね、わかる、という感覚にあらゆる情動を押し込めて、しばし口をつぐんでいる。
言葉を奪われたような気がする、というのは要するにそういった現象に対してで、私は怖くなってしまう。
自分は自分の語れる言葉を失いたくないのだ、多分。
仮に誰かが私とほとんど同じ(に見える)意見や感覚を持っていたとして、それを表明していたとして、こちらだって確かにそういう思いを持っていたのだとわざわざ記録しておくことは意味のある行為だと信じている。誰かがすでに語っていたからもう自分は言わなくてもいい、なんて、そんなことはないと考える。
存在しているひとりひとりが違った人間である以上、何か特定の物事について「言い尽くされてしまう」現象などほとんどありえない。仮にそう見えるとしたら、あえて悪意ある表現を選ぶとすると「怠惰」なのではないだろうか。寸分たがわず同じ人間などいないのだから。
言いたいことも考えたことも、この存在がこれからも続く以上は決して無くならないはずで。
だから、彼女の文章を読んでズブズブの共感のシロップに浸されたあとは、きちんと手足や頭の形状を取り戻そうと試みるのだった。もうめちゃくちゃに、あなたの言っていることわかるよ、とむせびながら、私は私でこんな世界を目の当たりにしているのだと、なかば意地のように残しておく。
基本的には昔の本、現代の小説ならフィクションばかり読んでいるのだが、それくらい随筆の方に心を寄せている存命の作家がひとり、いるのだった。
作家の顔なんていちいち見るものではないと思いながら、文庫カバーの折り返しに印刷されている著者の写真を眺めて、どこか憂いを帯びたまなざしに息を吐く。外側の造形うんぬんの話ではなくて、醸し出される雰囲気の魅力的な人なのだ。
そう。ズブズブである。