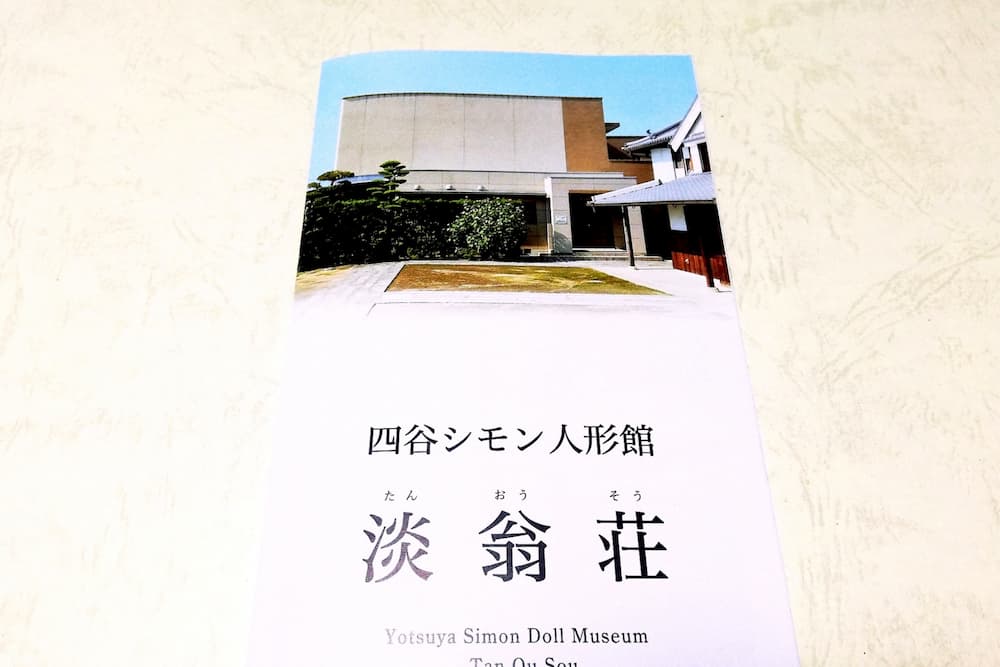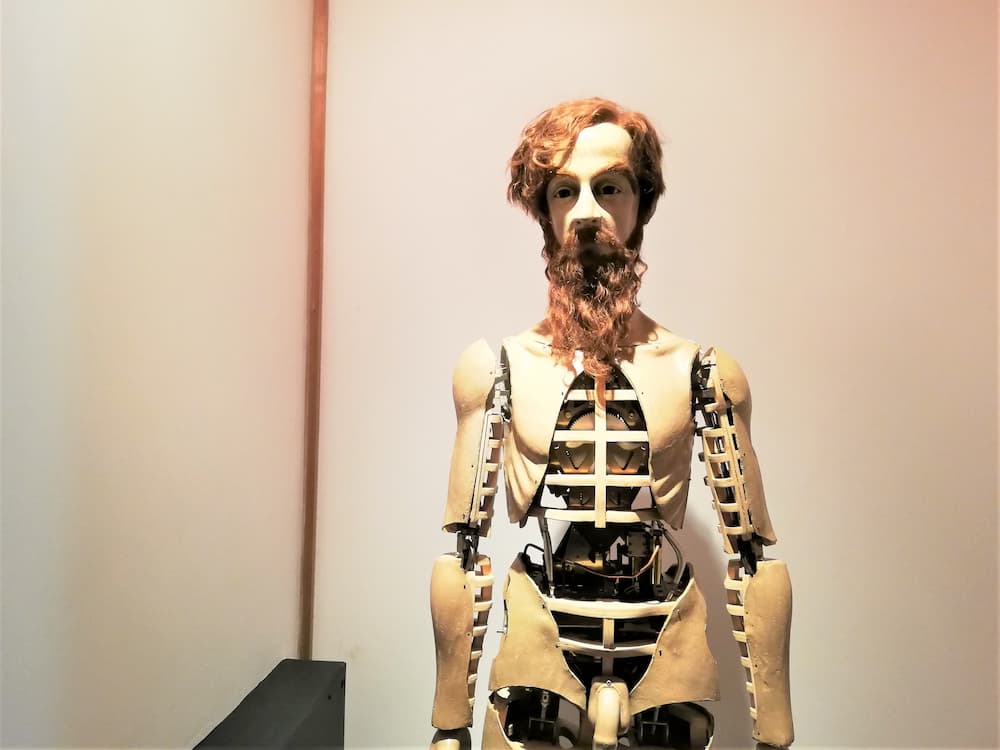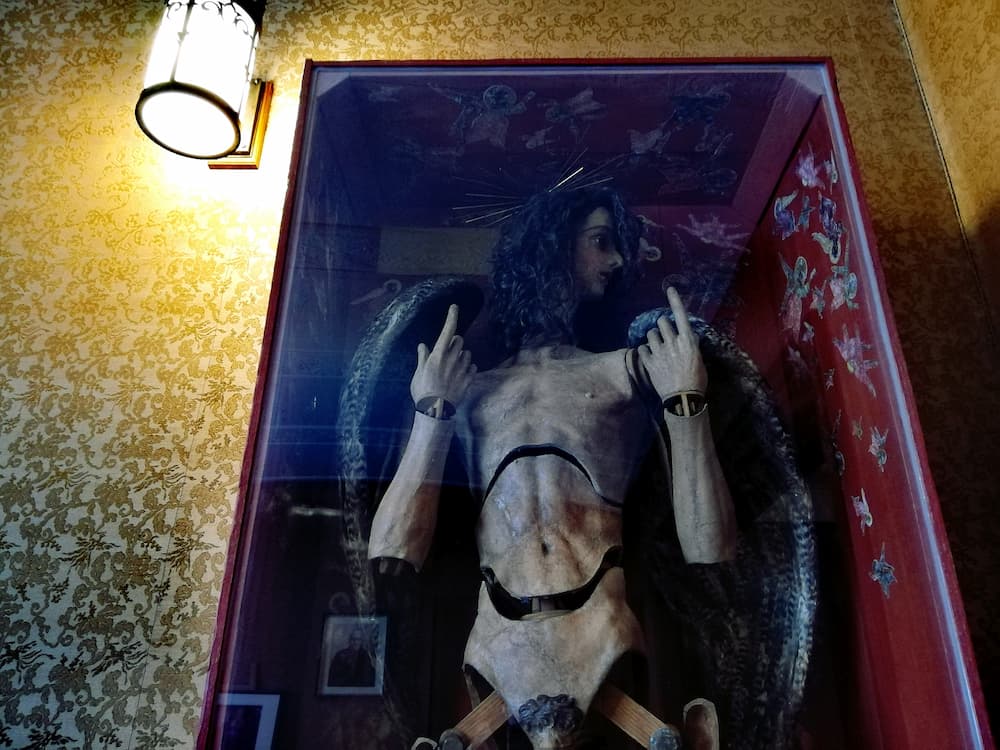太陽が地平線の向こうに消えてから活動を始める、夜に乗じて蠢くものたち(Night Walker)の多くは、昔から危険であったり、たくらみを胸に秘めていたりするものだと一般に言い表されてきた。
なぜだろう。でも、確かになんとなく想像は及ぶ。岩壁の洞穴や木を組んで造った住居、その周囲を跋扈する獣たちを警戒しながら眠りについた、古代の人々から受け継いできた感覚だろうか。これは。
……夜。
どこか妖しくても、いや、むしろそれゆえに興味を惹かれて、かつては光と暗闇によってはっきりと隔たれていた時間の境界を越え、双方を行き来してみたいと思う瞬間は人生の中で頻繁に訪れる。現代にいると危険を冒さなくても、祈祷師のように特別な資質を持っていなくても、比較的容易にそれができるのだ。目を開けたままで。
だからこそ、移動遊園地の電飾が鮮やかな色彩を帯びて公園を照らすような存在——安全を志向するのではなくて、人間を魅了するのに特化した灯り――に近付き、そこで一体何が起こるのかを、じっと息を殺して見届けてみたいと願ってしまう。


明治に登場した交通機関のひとつ、鉄道の車両にも、夜と昼の境をまたいで走行するものがある。日付が変わる前に出発し、朝に終点へ辿り着くような種類の。
地上に張りついたレールを基盤として、暁を待つのではなく、そこへ向かってひたむきに走るのが夜行列車だ。そう、真面目かつ「ひたむき」に、自らに与えられた職務に忠実に、両脇から迫る闇を振り切っていく。それは夜に属し揺蕩うものというよりかは、夜を通過していくものだと感じ、それゆえにサンライズ(Sunrise/日の出)の呼称は尚更ふさわしいもののように思われた。
2023年7月現在、日本国内で毎日定期運行する寝台特急というものは、サンライズ出雲とサンライズ瀬戸の2種類にまで減少している。
そんな「最後の寝台列車」に乗るため、早朝の対極に位置する宵の口をだいぶ過ぎて鉄道駅へ向かった関係で、何とも言えず新鮮な気分に……。行動の様式がいつもと全然違うから、果たして出発するのだか帰郷するのだか、判然としなくなる。心身ともにこんがらかる。そう、多分そのせいで、こうして旅行記を最終日の回想から始めているのかもしれない。



サンライズ瀬戸に乗車したのは復路。これは旅行最終日の話だ。
客室の種類は、B寝台のシングルツインだった。希望日の予約がなかなか取れないことで有名なサンライズの切符、夜中にe5489のサイトを適当に弄くり回していたらその便が取れたため、結果的に帰りの利用になったという経緯で。特にその日を希望して選んだわけではない。予約は、運次第。
シングルツインは狭い2段ベッドの部屋で、これの名目としては「基本1人部屋だが2人でも乗れる」というもの。1段目の寝台はシーツを剥がして折りたたむことで、上の写真のように「座席」の形にすることもできる。濃緑が車両外観の紅色と呼応していて楽しくなった。いい色だ。車掌さんが巡回してくるので、寝台券(改札に通さなかった方の細長い切符)を提示して、あとは自由に過ごすだけ。
個人的に、初めての寝台列車の利用を復路にするのは結構おすすめかもしれない。
慣れている人はいいが、音や揺れのパターンに慣れたり、立ったまま素早くシャワーを浴びる必要があるなどしてわりと体力を使うので、それを経て朝から旅行を開始するとなるとまあまあ疲れるのではないだろうか。出張や各種公演のための遠征など、早い時間に合わせた用事がない(どちらかと言うと寝台列車に乗るのが目的)なら、全てを終えた帰りに乗車してみるのも良いと思う。



始発駅からの乗車で、さらにA寝台シングルデラックス(シャワーカード付)以外の部屋を利用する場合、きっとシャワーカード購入の「列」に並ぶことになる。あるいは、下車してから現地の銭湯に行く? もちろん、それも選択肢のひとつ。
2023年7月現在330円のシャワーカードが買えるのは、高松駅始発・東京駅行きの上りだと、10号車。反対に下りならば3号車。プラットフォームでその表示がある場所に並ぶ。両替機も車内にあるけれど、あらかじめ自販機などを利用して小銭を作っておくのが吉だった。特に私は何かに手間取ってしまうとすぐに頭がおかしくなってくるので(!?)
シャワールームの脱衣所ではカードを機械に挿入し、さらに戻ってきたものを引き抜いて回収すると、無事シャワーが使用可になる。ブース内を覗いてきちんと残り使用時間が「6分」と表示されているか確認してみよう。緑のボタンを押してお湯が出ているあいだ時計は進み、赤いボタンを押せばお湯もカウントダウンも止まる。そんなに難しいことはない。ただ、シャワー使用後は「洗浄ボタン」を押してから去るのを忘れずに。
しかしドライヤー送風の弱々しさには閉口させられた。本当に「そよ風」を具現化したみたいにお上品な風しか出てこなくて、こんなんで髪の毛を乾かせるはずがあるまい! セミロングヘアをなめているのか? と憤慨しながら、部屋に帰ってタオルを駆使したのが印象的な思い出。ちなみにパジャマ(浴衣)は客室に置いてある。帯付き。



シングルツインの部屋、私は上段のベッドをもらった。入口上に荷物置き場があるので、そこにリュックサックやお土産などを収納してしまうと寝台上の空間が広々と使えて快適だった。操作盤にあるボタンを押す、すると窓を覆っていたカーテンがウィンウィンと自動で開いて、たくさんの街の灯りが進行方向とは反対側に流れ去っていった。
高松駅のホームを発進した車両は結構なスピードで進む。外の暗さに月の光が映えていた。この日のちょうど数日前が満月であり、晴れた夜空の闇を背景に、角度によっては徐々に欠け始めた満足そうな衛星の顔が見える。坂出駅を過ぎれば瀬戸大橋、車両は続く児島へ向かって海上をひた走る。
月と夜行列車……といえば思い出されるのは、19世紀イギリスで、世界で初めて狭義の旅行代理店を開業したと言われるトマス・クックが企画した「月光旅行(月光の旅)」のこと。これも夜に出発する列車旅の呼称で、昼間は労働に従事している忙しい人々のために考案された旅行プランだった。
私はその、皓々とした月の光を受けて線路上を走る、列車の姿が連想される名前も好きだ。乗車した日の出(サンライズ)の名称と並べてみれば殊更に。


電灯の光で満たされた廊下はまさしく過去と未来の両方に繋がっている。
新橋—神戸間に、日本初の夜行列車が東海道線を走行し始めたのが明治22(1889)年のこと。その2年後、今度は日本鉄道が上野—青森間を約26時間半で結んだ。やがて「寝台」そのものが列車に組み込まれるまでにはさらに9年ほどを要し、明治33(1900)年4月に、山陽鉄道が食堂車と寝台車を連結した便の運行を始めた。同年の10月に官設鉄道も英・米から輸入した寝台車の活用を開始したそうだ。
参考:【企画展 The Sleeper Train~寝台列車の軌跡~|京都鉄道博物館】
https://www.kyotorailwaymuseum.jp/museum-report/the-sleeper-train/
1等と2等車しかなかった時代の寝台列車は今よりずっと高級路線だったようだけれど、単純な乗り心地でいえば、比較的手軽な値段で乗れる現代のサンライズの方が遥かに勝っただろうと想像する。
もちろん、19世紀初頭のヨーロッパで「拷問箱」だとか「肋骨折り機」などの禍々しい名前で呼ばれていた悪名高き駅逓馬車(参考:W・レシュブルク「旅行の進化論」 林龍代・林健生訳)と比べてしまえば、明治時代の寝台列車も天国だと表現してしまって差し支えない。



前回の四国旅で長距離フェリーを利用した経験からも感じたのは、私はこの手の乗り物に乗るのがわりと好きで、比較的よく眠れる性質らしいということだった。揺れも、音も、客室に鍵をかけられる時点であまり気にならなくなる。毛布にくるまれる、安全な空間が確保されていることの方が睡眠には重要な要素らしい。
ちなみに部屋の外に出るときは暗証番号をドア横のキーで設定し、戻ってきたらそれを打ち込む、という形で施錠と開錠を行える。
上りの便は日の出の時刻になるとちょうど富士山が窓の外に姿を現すから、このタイミングでお弁当などを持って、ラウンジのスペースに移動するのもおすすめ。サンライズに乗ってサンライズを見る……もちろん、瀬戸内海に面する土地で手に入れた駅弁を存分に楽しみながら。車内には飲料の自動販売機があるが、食べ物を買える設備は無いことに注意されたし。

高速で横に移動している。まるで、地面の上に設けられた普通の宿泊施設のような寝台列車の車両が。
建築物好きとしてはこれも広義の建物として捉えたい。壁があり、屋根もあり、さらに扉があって、窓もある……そういう構造物のひとつ。それがしかも毎日、決まった時間に線路上を走るとは、想像以上に面白いことだ。しかも客室のひとつひとつに乗客を、その前後の予定と人生ごと積載して動いている。
それについて考える空隙を与えてくれるという一点だけでも、時間を費やして寝台列車を利用する価値は大いにある。何より、楽しい。
東京駅のプラットフォームに到着して行先が「回送」に変わるサンライズ瀬戸、その車体の紅色ではない方の部分は、牛乳を多めに投入したミルクティーによく似ていた。帰宅する前に喫茶店に寄って、紅茶が飲みたくなった。
香川旅行記は(2)へ続く……

はてなブログ お題「夜行列車の思い出」